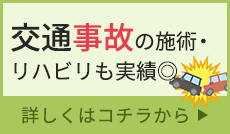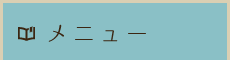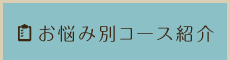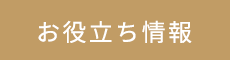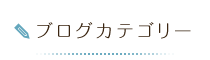岡山の交通事故施術 | 岡山駅徒歩5分のさくら整骨院
交通事故に遭った後、首や肩、腰、背中に痛みやだるさ、しびれを感じていませんか?
見た目には異常がなくても、症状が続くことで不安になる方も少なくありません。
さくら整骨院では、薬では届かない身体の構造と神経・血流のバランスから整え、
根本原因にアプローチする交通事故施術を行っています。
交通事故後の身体の不調の主な原因
交通事故後の症状は、首や腰のケガだけが原因ではありません。
脊柱や骨盤、関節、筋肉、神経、血流など、全身のバランスが関わっています。
首や頸椎の損傷・筋緊張 → 首・肩の痛み、頭痛、手のしびれ
腰椎や骨盤の歪み → 腰痛、下肢のしびれ、姿勢不良
脊柱全体の歪み → 筋肉の緊張や血流障害 → 慢性痛やだるさ
神経や血流の乱れ → 痛み・しびれ・だるさの慢性化
これらを総合的に整えることで、事故の衝撃によって生じた身体の過敏状態や歪みを改善していきます。
つらい症状を本気で改善したい方へ
痛み止めや一時的な対処ではなく、脊柱・関節・筋肉・神経・血流のバランスを根本から整えることで、痛みやだるさ、しびれの改善を目指します。
交通事故後の不調に悩まされ ることのない、快適な日常を取り戻すために
ることのない、快適な日常を取り戻すために
交通事故の痛みを改善する施術って?
「事故のあとから、ずっと体の調子が悪い」
「病院では“異常なし”と言われたけど、首や腰が痛い」
「天気や疲れで痛みが酷くなる」
交通事故のあとに起こる身体の不調は、
実際に怪我をした傷とは別に、目に見えるケガだけでは説明できない痛み
が続くことが非常に多く
レントゲンやMRIで「骨に異常なし」と言われても、
痛みやだるさ、しびれ、倦怠感、頭痛などが続くことがほとんどです。
それは、事故によって生じた身体の内部構造の乱れと神経の過敏化が、
時間をかけて全身に影響を及ぼしているから
交通事故が身体に与える「本当のダメージ」
事故の衝撃は、瞬間的に大きなエネルギーを身体へ伝えます。
このとき、筋肉・靭帯・関節包・神経・血管などの軟部組織が細かく損傷し、
体は一瞬で「防御反応」を引き起こします。
筋肉は過緊張し、関節はロックし、神経系は危険信号を記憶します。
一見すると「大きなケガはない」ように見えても、
身体の深部では、常に緊張と警戒が続いている状態になるのです。
この持続的な防御反応こそが、
「むち打ち」「腰の重だるさ」「しびれ」「頭痛」などの
事故後のさまざまな症状を引き起こす根本的な原因です。
交通事故治療での注意点と早期対応の重要性
なぜ「早めの行動」が回復を左右するのか?
交通事故後、「痛みはたいしたことない」「レントゲンで異常なし」と言われても、
放っておくと症状が長引くことや、突然強い痛みがでてくるようになるがあります。
これは単なる「放置の結果」ではなく、
身体の内側で時間とともに進行する生理学的プロセスが原因で。
まずこのプロセスを理解することが、早期の行動につながり
交通事故の痛みを根本的に改善することにつながっていくのです
組織修復の時間軸を知る
ヒトの一般的な傷の回復過程は、傷を受けると身体は段階的に反応するようになっています。
代表的な段階は
出血止め → 炎症期 → 修復・増殖期 → 再建・リモデリング期
といった流れで
炎症期は通常数日で
修復〜再建期は数週間〜数か月にわたって続き
筋・靭帯などの軟部組織の損傷も同様の段階で治癒しますが
適切な循環や動きがないと不完全修復になりやすい点が重要です。
炎症と「防御性筋緊張」が悪循環を作る仕組み
事故直後の損傷部位では炎症性メディエーターとよばれる
サイトカイン、プロスタグランジン等が放出され
血管の拡張や神経終末の感受性上昇を引き起こします。
これに対して体は反射的に筋を収縮させ、防御体制を作ります。
しかし持続した筋緊張は局所血流を低下させ、老廃物や炎症物質の除去を妨げ
さらに痛みを増幅させる──という負のループが成立。
特に頸椎周囲の深層筋は小さな損傷でも長期的なこりや
可動域制限を残しやすいことが臨床上でも多く報告されています。
末梢→中枢へ「神経系の過敏化」が慢性化を促す
急性の炎症や持続する侵害刺激は、末梢の侵害受容器を持続的に活性化し、
やがて「脊髄」や「脳」の痛み処理回路の興奮性を高めます
これを中枢感作といい
中枢感作が起きると、軽い刺激でも強く痛みを感じる過敏症を引き起こしたり
周辺領域に痛みが広がったりするようになります。
さらに痛みについての詳しい解説はコチラから
⬇︎
このプロセスが一度進むと「痛みだけを消す」だけでは改善しづらくなり、
早期に侵害刺激を抑え、正常な入力へ戻す動きが重要になります。
放置すると起きる「構造的・機能的」な変化
早期に動作や循環が回復しない場合
筋繊維の瘢痕化や筋膜癒着 → 可動域制限
関節包・靭帯の拘縮 → 関節の機械的制限
関節位置感覚(プロプリオセプション)の低下 → 不安定な動作パターンと二次障害
といった、変化が進みやすくなり
これらは回復を遅らせるだけでなく、別部位への過負荷を招き
慢性痛ネットワークを作る原因になります。
早期対応が有効な理由
また、交通事故直後の体は
交感神経の興奮や筋緊張反射、炎症反応が一気に高まり
身体を「守る」状態に入ります。
この防御反応そのものは正常な仕組みですが
過度に長引くと慢性化の「元」になります。
炎症反応と循環
事故直後は、損傷した組織では血管が拡張し、炎症性サイトカインが分泌されます。
これは修復を促す一方で、血流停滞・浮腫・疼痛受容器の感作を引き起こします。
ここで適度な可動域運動や軽い負荷を行うと、
筋ポンプ作用により循環が改善し、炎症産物の除去が促進されることがわかっています。
神経系の過敏化の防止
逆に安静を続けすぎると
脊髄レベルで侵害受容ニューロン(痛みを伝える神経)の興奮が高まり
「痛みの記憶」が形成されやすくなります。
これは中枢性感作と呼ばれ、軽い刺激でも痛みを感じる慢性痛の原因になります。
早期に軽度の動きや触刺激を入れることで、脳が「安全な動き」として再学習し、
痛み信号の過敏化を防げると考えられています。
筋・関節機能の維持
筋肉や靭帯は、動かさない期間が続くと
伸張反射や固有感覚受容器(筋紡錘・ゴルジ腱器官)の活動が低下し、
「身体の位置感覚」が鈍ります。
その結果、姿勢保持やバランス機能が低下し、二次的な筋緊張や関節痛を引き起こします。
早期に可動域を保つことは、筋・関節センサーの再活性化につながります。
このように、
単に「早く治療する方がいい」というよりも
神経・筋・循環の各システムが“正常に回復できるタイミング”を逃さないことが重要です。
交通事故後の評価で押さえておきたい「重要チェック項目」
交通事故の症状は「衝撃の方向・強さ・タイミング」によって
まったく異なる経過を辿ります。
一見「軽い追突」でも
数日後に「痛みやしびれ、自律神経症状」が出てくることも少なくありません。
だからこそ、臨床で必ず確認すべき項目と、生理学的・病態学的な意味を理解することが重要なのです。
事故状況と発症タイミング
【ポイント】
「事故はいつ、どこで、どのように起きたのか?」
「車のどの部分に衝撃を受けたのか?」
「そのときの速度は? 停止中?発進中?徐行中?」
「症状は事故直後から? それとも数時間〜数日後か?」
【なぜ重要なのか?】
それは衝撃の方向によって
後方追突では「過伸展」ストレス(頸椎後方構造への負荷)
正面衝突では「過屈曲」ストレス(椎間板・靭帯前方)
側面衝突では「回旋」ストレス(筋膜・神経根牽引)が生じます。
この力学的負荷の方向が、そのまま損傷部位と症状パターンを決定します。
また、軟部組織損傷は画像に写らないため、症状が遅れて出るタイミングも診断のカギとなります。
痛みの性質と広がり
「どこからどこへ広がるか?」
「痛みの強さは0〜10でどのくらいか?」
「動かすと症状や痛みが変わるのか?動くと強まる?安静時に強い?」
「電気が走るような痛みはあるのか?」
【重要なポイント】
鋭い・動作で悪化 → 関節包や筋腱性の機械的痛み
焼ける・ジンジン・電撃様 → 神経障害性痛(神経根・末梢神経)
放散が皮節に一致 → 神経根障害(椎間孔レベル)
こうした「痛みの質+分布パターン」は、画像よりも明確な病態指標となります。
可動域と痛みの関連
観察ポイント
能動的な動きでの痛み → 筋性・関節機能不全
受動的な動きでの痛み → 関節包性問題や機械的ブロックの可能性
ROMの制限パターンを把握することで、どの組織が「過剰に守っている」のかを見極められます。
神経学的サイン(筋力・感覚・腱反射)
筋力(MMT 0–5):上肢・下肢の主要筋群を評価
感覚:軽触・痛覚・振動覚を比較し、皮節パターンを確認
腱反射 上肢:上腕二頭筋(C5/6)、橈側手根伸筋(C6)、上腕三頭筋(C7)
下肢:膝蓋腱反射(L4)、アキレス腱反射(S1)
感覚障害が皮節に沿って出る場合、神経根の絞扼レベルを高い精度で推定できます。
自律神経系の変化
「めまいはあるか?」
「動悸・冷や汗・立ちくらみ・吐き気・胃腸不良は?」
「睡眠は取れているか? 入眠困難、途中覚醒、早朝覚醒」
交通事故後は、身体の防御反応により交感神経優位が続く傾向があります。
その結果として
-
筋緊張の持続(血流低下・疼痛の悪化)
-
内臓・消化器の機能低下
-
睡眠の質の悪化
など、慢性的な自律神経失調を引き起こします。
こうした症状を見逃さず、神経学的・構造的・自律神経的評価を総合して捉えることが、
「痛みの根本要因を見抜く第一歩」です。
特に、頸椎・頸部筋の損傷は固有受容や頸部-脳幹の感覚入力を乱し
頸性めまいや自律神経症状を訴えることがあります。
頸部損傷後に出る非回転性のめまいや動悸、吐き気などはこの領域に関連する場合がありますが、鑑別診断として内耳性めまい・脳血管障害(椎骨脳底循環障害)を除外することが重要です。
めまい障害についての詳しい解説はコチラ
⬇︎
筋肉・関節・神経の連動からみた不調
交通事故の衝撃は、首や腰といった局所だけでなく
筋肉・関節・神経が互いに連動している仕組み全体を変化させます。
なぜ「連動」が重要なのか
身体はパーツの寄せ集めではなく、
骨格・関節・筋膜・筋・神経・血流が連携して動く「システム」です。
一か所に衝撃が入ると、その力は周囲へ連鎖的に伝わり
元の運動パターンが書き換えられます。
その結果、痛み・可動域制限・しびれ・慢性疲労といった症状が現れます。
慢性化の段階的メカニズム
直接的な組織の損傷
事故の衝撃で筋繊維・靭帯・関節包が傷つくと、局所で炎症が始まります。
炎症により痛み刺激が増えることで、周囲の組織も“警戒”状態になります。
→ 「押すと痛い」「腫れ感」「最初は動けるが動くと痛む」
防御性筋緊張と運動パターンの再配線
組織を守るために筋肉が防御的に緊張し硬くなるのですが
これが、長引くと「ある筋は過活動、ある筋は働きが弱まる」という
アンバランスな状態が固定化します。
→深層頸層筋が弱り、表層筋が緊張する
これが元々の自然な動きができなくなりに二次的負担が別の部位かかり
さらに改善を遅らせることになります。
関節の滑走性と関節機能障害
関節包や関節面の機械的障害で、関節の「すべり」が悪くなります。
関節の動きが悪いと、その周囲の筋が過緊張になり、血流・代謝が落ちる。
→ 可動域制限、特定の動作での鋭い痛みが現れやすくなります。
関節受容器
関節受容器や筋紡錘は身体位置や動きの感覚を脳に伝えます。
事故の際の衝撃や衝撃による歪みでこの入力が乱れると、脳は正確な運動指令を出せなくなります。
これがバランス低下や不安定な動作の原因になります。
→ 「よくふらつく」「いつもより力が入りにくい」といった症状を引き起こします。
末梢神経の神経症状
関節のわずかなズレや、腫れや筋の硬さが神経を刺激すると
腕や脚へのしびれ・電気が走るような痛みの放散痛が現れます。
神経炎と呼ばれる、神経そのものの炎症や
軸索損傷がある場合は感覚鈍麻や筋力低下が見られます。
→ 「皮膚感覚の変化」「特定の筋力低下」「反射の変化」
痛みの学習
末梢からの持続的な侵害刺激は
脊髄・脳の痛みを処理する回路を過敏にする中枢感作を引き起こし
これが結果的に、些細な刺激でも強い痛みを感じたり、痛みが広がるような現象を引き起こし、痛みスケールを上昇させたり、鎮痛薬が効きにくくなる症状を誘発します。
循環・代謝低下が症状を長引かせる
筋緊張や関節拘縮により局所の血流・リンパ流が悪化すると
炎症産物や老廃物が除去されにくくなります。
代謝環境が悪いと組織修復が遅滞し、慢性の疼痛源が持続します。
→ 冷感やだるさ、慢性的な張り感として症状がでることも。
二次的代償と全身連鎖
本来の可動性を補おうとして、他の関節や筋が過剰に働きます。たとえば、首の動きを腰や肩で代償すると、そこに新たな痛みが出ます。
→ 痛みの「原因」がわかりにくくなり、治療が長引く原因となります。
急性〜慢性にかけた時間経過のポイント
急性期(受傷直後〜数日)
→ 主に炎症と防御性筋緊張。痛みは局所的で明瞭。画像で確認される場合あり。
亜急性期(数日〜数週)
→ 筋連鎖と関節機能障害が固定化し始める。可動域低下や放散痛が目立つ。
慢性期(数か月〜)
→ 中枢感作や瘢痕化、運動習慣の変化が定着。疼痛の感覚が変化し、日常機能が低下しやすい。
脊柱の構造と生理学的役割
脊柱は24個の椎骨が積み重なり、その内部を脊髄が通過しています。
脊髄からは、左右に脊髄神経根が分岐し、全身の筋肉・感覚・内臓に指令を送っています。
つまり、脊柱のわずかな歪みや捻れが起こると、
「骨がズレた」というよりも、神経伝達・筋緊張・血流調整といった生理機能そのものが乱れやすくなるのです。
衝撃によって起こる脊柱の反応
交通事故では、瞬間的に強い衝撃が身体に加わります。
このとき、脊柱はしなるように動かされ、頸椎や腰椎に大きなストレスがかかります。
- 深層筋(多裂筋・回旋筋)が反射的に収縮
→ 脊柱を守る防御反応として筋肉が硬直。
→ 持続的な筋緊張で関節の動きが制限される。 -
関節包・椎間関節の圧受容器が過敏化
→ 関節の「動きを検知するセンサー」が誤作動し、
脳に危険信号が送られ、痛みが長期化。 -
脊柱起立筋・胸腰筋膜の張力バランスが崩れる
→ 筋膜の連動で首から骨盤まで緊張が波及。
→ 一部の筋に過負荷、他の部位が機能低下。 -
交感神経系の興奮
→ 頸椎上部(C1〜C3)や胸椎上部(T1〜T4)の歪みは交感神経節を刺激し、
動悸・めまい・睡眠障害・消化機能低下など自律神経症状を引き起こすことがあります。
わずかな歪みでも症状が出る理由
脊柱の歪みは、レントゲンでは「正常範囲」とされることもあります。
しかし、生理学的には数ミリ単位の関節位置の変化でも、
その周囲を通る神経・血管・リンパ流に微細な圧迫や牽引を与えることがあります。
神経根の圧迫 → しびれ・放散痛
血流の停滞 → 筋代謝の低下、疲労物質蓄積
静脈・リンパの滞り → 炎症の遷延、浮腫
これらが積み重なると、体は「痛みを守る姿勢」をとり始め、その歪んだ姿勢のまま筋肉・関節・神経の使い方が再学習されて、これが慢性化のはじまりとなります。
脊柱を整える意味
脊柱の歪みを整えることは、単に骨を「元に戻す」ことではありません。
生理学的には
「神経の伝達をスムーズにする」
「筋膜や関節包のセンサーを再調整する」
「血液・リンパ・脳脊髄液の循環を改善する」
これらの機能的ネットワークを回復させることが目的です。
脊柱が柔軟に動くことで、身体は“力を逃がす”ことができ、
神経・筋・循環の過緊張が自然と解けていきます。
全身連動としての脊柱
脊柱は、頭蓋骨・肩甲骨・骨盤と連動して動く一本の軸です。
そのため、一部の歪みが全体に波及するのは自然なことです。
頸椎のねじれ → 肩こり・頭痛・めまい
胸椎の硬さ → 呼吸浅化・背中の張り
腰椎の偏位 → 骨盤の傾き・坐骨神経痛
事故後の「首だけ」「腰だけ」という捉え方では不十分で、
脊柱全体の動きの調和を取り戻すことが、本当の回復につながります。