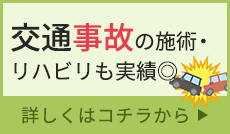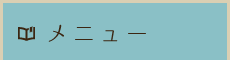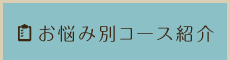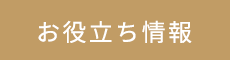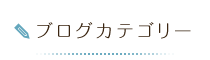岡山の耳鳴り治療 | 岡山駅徒歩5分のさくら整骨院
「キーン」「ジージー」「シャー」など、耳の中で音が鳴り続ける。
病院で“異常なし”と言われても、音が止まらず不安になる。
そんな耳鳴りでお悩みではありませんか?
さくら整骨院では、薬では届かない身体の構造と神経のバランスから整え、
根本原因にアプローチする耳鳴り施術を行っています。
耳鳴りの主な原因
耳鳴りは「耳の中」だけの問題ではありません。
神経・血流・姿勢・ストレスなど、全身の影響が関係しています。
内耳や聴神経の緊張・血流不足 → キーンとした高音性耳鳴り
頸椎や顎関節の歪み・筋緊張 → 片側だけ鳴る・首こりと併発
ストレスや自律神経の乱れ → 寝る前や静かなときに悪化
これらを総合的に整えることで「音」を作り出している身体の過敏状態を改善していきます。
つらい耳鳴りを本気で改善したい方へ
薬や一時的な対処ではなく、
神経・血流・姿勢を根本から整えることで、耳鳴りの軽減と再発防止を目指します。
耳鳴りに悩むことのない、いつもの日常へ。
なぜ病院で「異常なし」でも耳鳴りが続くのか?
多くの方が耳鼻科を受診し、聴力検査やMRI検査を受けられます。
そこで「耳には異常がありません」と言われ、この耳鳴りがどうすれば改善するのか?
と悩まれる日々。これはよくあるケースです。
なぜなら、耳鳴りの多くは「耳そのもの」だけでなく、首・顎・姿勢・自律神経など全身のバランスの崩れから起こるからです。
- スマホの見過ぎによるストレートネックと頸椎の歪み
- 無意識の食いしばりや顎関節の緊張
- 慢性的なストレスや睡眠不足による自律神経の乱れ
これらが複雑に絡み合い、耳への血流不足・神経の過敏化・脳の過剰反応を引き起こしています。ですから、耳だけを診ても原因が見つからないのです。
耳鳴りの仕組みと原因
耳鳴りは「単に耳の中で音が鳴る」という単純な症状ではありません。
実は、耳・神経・血流・姿勢・自律神経といった複数の要素が複雑に絡み合って起こる、全身性の症状なのです。
ここでは、耳鳴りがなぜ起こるのか、その仕組みと原因を詳しく解説します。
内耳・聴神経からの影響
有毛細胞の損傷が「音のないノイズ」を作る
耳の奥にある内耳と呼ばれる部分には、音の振動を電気信号に変換する「有毛細胞」という細胞が存在します。
この有毛細胞が「加齢による衰え」や、「イヤホン・工場・ライブなどによる長時間の騒音」などで損傷し血流が不足することで栄養が届かなくなるといった理由でダメージを受けると、正常に機能しなくなってきます。
すると脳は「音の情報が足りない」と判断し、不足した信号を補おうとして過剰に反応します。この過剰反応が、実際には存在しない「耳鳴り」という音として知覚されるのです。
聴覚神経の過敏化
有毛細胞からの信号は、聴神経を通じて脳へ送られます。
この伝達経路で神経の興奮バランスが崩れると
- 神経のスパイクと呼ばれる自発発火が起こる
- 脳がそれを「音」として誤認する
- 音が鳴り続けているように感じる
これは「中枢性の過感作」と呼ばれ、耳鳴りが慢性化する大きな要因となっています。
頸椎・頭蓋骨の歪みによる影響
首の歪みが耳への血流を妨げる
耳への血液は、椎骨動脈という首の骨(頸椎)の横を通る血管から供給されています。
デスクワークやスマホで頭が前に出る姿勢や、首の筋肉の過度な緊張、頸椎1〜3の配列の乱れなどによって椎骨動脈が圧迫され、内耳への血流が低下し有毛細胞や聴神経の働きが悪くなることで、耳鳴りが発生・悪化します。
頭蓋骨のわずかな「ズレ」も影響する
頭蓋骨は複数の骨が組み合わさってできており、頭蓋リズムという非常に繊細な動きで
わずかに動いています。
その中でも特に耳鳴りと関係が深いのが
耳の穴がある骨で内耳が収まっている「側頭骨」
首との接合部・神経や血管の出入口になる「後頭骨」
頭蓋の中心で全体のバランスを司る「蝶形骨」
の3つ。これらの位置関係がわずかにズレることによって
内耳液と呼ばれるリンパ液の圧力バランスが崩れ、静脈・リンパの流れが滞ることによって、聴神経など神経が刺激されやすくなることで、耳鳴り・耳閉感・めまいなどが引き起こされます。
顎関節と咀嚼筋
顎と耳は「すぐ隣」
顎関節は実は耳のすぐ前にあり、構造的に非常に近い位置にあります。
噛みしめ癖・食いしばり
歯ぎしり
片側だけで噛む癖
噛み合わせの異常
などによって咬筋・側頭筋・外側翼突筋などが過度に緊張する
側頭骨に歪みが生じ、中耳と喉をつなぐ耳管と呼ばれる管が圧迫され、鼓膜や耳小骨に微細な圧力変化が起こりやすくなり、結果として、耳鳴りや耳の詰まり感が出現します。
神経の混線
顎関節を支配する三叉神経と、耳を支配する顔面神経・迷走神経の中枢は脳幹で近接しているので、顎周囲の筋肉や関節からの異常な信号が、聴覚系と混線(を起こし、耳鳴りとして知覚されることがあるのです。
血流・循環からみる耳鳴り
内耳は「血流の影響を受けやすい」
内耳は非常に繊細で、酸素や栄養の供給が少しでも滞ると機能が低下してしまうので
頸椎や胸椎の歪みによる首・肩・背中の筋肉の緊張や自立神経の乱れによる血管収縮などによっても有毛細胞の代謝が悪化し、神経が過敏になり、耳鳴りが起こります。
拍動性耳鳴り
心拍に同期して「ドクドク」「ズンズン」と聞こえる耳鳴りは血管の流れ異常が原因のことが多く、多くの場合が「頸動脈の狭窄や蛇行」「静脈洞の圧力変化」「血管の炎症」による影響で
これは頸部や頭部の動脈・静脈の血流が不規則になると、その振動が内耳に伝わり
脳や聴覚神経はこれを「音」として認識するため、心拍に同期した耳鳴りとして聞こえるという現象で
拍動性耳鳴りの場合も、血管だけでなく周囲の筋骨格・神経の状態が影響するので頭部への血流・神経伝達を改善することが重要です。
脊柱全体の歪みと神経への影響
「腰や骨盤の歪み」が耳に影響する理由
一見関係なさそうですが、骨盤や腰椎の歪みは、脊柱全体の連鎖を通じて頸椎・頭蓋に波及します。
例えば
骨盤が傾くことで → 腰椎がねじれる
腰椎のねじれは → 胸椎が代償的に回旋する
胸椎の歪み → 頸椎に負担がかかる
頸椎の緊張 → 頭蓋・顎関節に影響
といった感じで「下からの歪み」が積み重なり、
最終的に耳周囲の構造バランスを大きく変化させます
硬膜の張力が脳幹を引っ張る
硬膜と呼ばれる脳と脊髄を包む硬い膜は、頭蓋の内側から骨盤の真ん中の仙骨まで一つの管のようにつながっています。
骨盤や腰椎が歪むとで、この硬膜を引っ張る、テンションが生じて脳幹にある聴覚神経核を刺激し、聴覚処理のバランスが崩すことで、耳鳴りを悪化させるのです。
自律神経の乱れ
寝る前や静かな場所で耳鳴りが強くなる理由
日中は周囲の音が、日常の生活音でかき消されていた小さな耳鳴りが
夜の静かな環境では脳が「音を探そう」として感度を上げるため、より強く感じられます。
また、夜間は副交感神経が働きリラックスするタイミングですが
自律神経のバランスが崩れていると、かえってさらに耳鳴りへの注意が向いてしまい、交感神経の活動が高まり、さらに耳鳴りを感じやすくなることも。
筋膜の連鎖
身体は「部分」ではなく「全体」でつながっている
筋肉を包む筋膜は、全身でつながった連続体で
足裏の筋膜 → ふくらはぎ → 太もも → 骨盤 → 背中 → 首 → 頭
といった流れで、足や骨盤の歪みが筋膜を通じて頭部まで伝わり、側頭骨や後頭骨の位置・緊張に影響します。
実際「足首の捻挫の古傷」や「骨盤の左右差」「猫背や反り腰」が回り回って耳鳴りの一因になっていることも多々あります。
耳鳴りは「耳だけ」の問題ではない
耳鳴りの原因は一つではなく、以下のような多因子が複雑に絡み合って起こります。
| 要因 | メカニズム |
|---|---|
| 内耳・聴神経 | 有毛細胞の損傷 → 神経の過敏化・誤作動 |
| 頸椎の歪み | 椎骨動脈の圧迫 → 内耳血流低下 |
| 頭蓋骨のズレ | 側頭骨・後頭骨の緊張 → 内耳圧変化 |
| 顎関節・咬筋 | 噛みしめ・咬合異常 → 神経の混線 |
| 脊柱全体の歪み | 硬膜の張力 → 脳幹への影響 |
| 血流・循環障害 | 筋緊張・姿勢不良 → 酸素・栄養不足 |
| 自律神経の乱れ | ストレス・疲労 → 交感神経優位 → 過敏化 |
| 筋膜の連鎖 | 全身のアンバランス → 頭部への波及 |
だからこそ、耳だけを改善ても根本解決にはならないのです。
耳鳴りとは「脳が作り出す音」
外から音が聞こえていないのに、脳が「音がある」と誤認してしまう――
これが耳鳴りの本質です。
実際には存在しない音を、聴覚中枢が勝手に知覚してしまう状態。
その背景には、内耳から脳に至るまで、複数ステップで生理学的な異常が起こっています。
有毛細胞が「誤った信号」を発する
内耳の中にある蝸牛と呼ばれ、音の振動を電気信号に変換する有毛細胞が損傷することによって、さまざまな異常な反応が起こります。
異常反応が起こる仕組み
- 有毛細胞の自発放電 → 音の刺激がなくても、勝手に電気信号が発生してしまう
- 蝸牛神経への誤伝達 → 実際には「音」がないのに、神経が活動してしまう
- 脳の聴覚皮質が”音”として知覚 → 脳は「音が聞こえている」と判断し、耳鳴りとして感じる
このプロセスによって、内耳の障害が「聞こえない音を音として」を脳に送り続けているのです。
聴覚路の興奮バランス異常
「音が足りない」と脳が勘違いする
蝸牛からの信号は
蝸牛 → 脳幹の蝸牛神経核→中脳の下丘→視床の内側膝状体→大脳の聴覚皮質
の経路で伝達され、その伝達は、興奮性の「グルタミン酸」と抑制性の「GABA」の神経伝達物質がバランスを取りながら、音の情報を正確に処理しています。
脳が勝手に「音を増幅」してしまう
ところが、有毛細胞が損傷してしまうと
入力信号が減少することで、脳が「入力が減った=静かすぎる」と誤認してしまい
その不足を補おうとして、神経の興奮を過剰に増幅してしまうということが起こってしまいます。
その結果、自発的なスパイク発火と呼ばれる反応が増加し、実際には音がないにもかかわらず「耳鳴り」という感覚として知覚するようになります。
つまり、脳が過剰に敏感になり、ノイズを拾いすぎている状態なのです。
中枢性耳鳴り「幻聴化」
脳が「音の地図」を書き換えてしまう
耳鳴りが長期間続くと、脳の聴覚野や辺縁系とよばれる情動をコントロールする領域に
機能的なリモデリング(再編成)が起こります。
再編成って何?
- 聴覚皮質でのマッピング再構築
本来「高音を処理する領域」が、隣の周波数領域を侵食し、過剰に反応するようになる - 扁桃体・前帯状皮質の関与
情動系が過敏になり、「不安」「緊張」といった感情が耳鳴りを増幅させる - 海馬の関与による記憶の固定化
脳が「耳鳴り=危険信号」として学習し、記憶に刻み込んでしまう
結果として
音が存在しなくても脳が音を作り出し、かつ”気になる”状態が固定化されてしまいます。
これが「中枢性耳鳴り」で、単に耳を改善するだけでは改善しにくく改善まで長期化してしまう理由の1つ。
体性感覚との相互作用
「首や顎を動かすと耳鳴りが変わる」理由
頸部・顎関節・咀嚼筋・後頭部の筋肉などからの体性感覚入力が、脳幹にある
蝸牛神経核に直接作用しているということで
メカニズムとしては
顎関節症や頸部筋の緊張により、体性感覚入力が異常化することで、この信号が聴覚系への入力と混線し、「音」として知覚されます。
特徴としては首や顎を動かすと耳鳴りの大きさ・高さが変わるという点で
これは筋・神経系の乱れが生理的ノイズを音として誤認する現象で構造を整えることで改善が期待できるという根拠にもなっています。
精神・情動からみる耳鳴り
「音の大きさ」と「つらさ」は別物
耳鳴りの「うるささ」や「つらさ」は、音の強さだけでは決まりません。
むしろ、脳の評価システム(扁桃体・前頭前野など)がどう反応するかで決まります。
悪循環の形成
不安・抑うつによって扁桃体が過活動することで耳鳴りに注意が集中し、さらに大きく感じる。これが睡眠不足とさらなるストレスとなり、視床下部・自律神経反応が過敏に。
内耳の循環がさらに悪化することで音のループと情動反応の悪循環が形成されてしまいます。
つまり、耳鳴り自体が不安を生み、不安が耳鳴りを悪化させるという、
抜け出しにくいサイクルができあがってしまうのです。
耳鳴り改善アプローチ
ここまで、耳鳴りがいかに複雑で、全身の構造・神経・血流・自律神経が関わる症状かを解説してきましたが
では「どのように耳鳴りに向き合い、改善を目指すのか?」をお伝えします。
さくら整骨院では「全身調整」により、耳鳴りの根本原因にアプローチします。
身体はすべてつながっている
血液・リンパの流れが改善の基本
身体には自己治癒力がある
局所ではなく、全体を整える
耳鳴りを「耳だけの問題」として捉えるのではなく、
頭蓋・頸椎・脊柱・骨盤・筋膜・神経・血流・自律神経という全身を改善することで、耳鳴り改善の身体作りを行っていきます。
1. 構造を整えることで「血流」を改善
耳鳴りの多くは、内耳への血流不足が関与しています。
頸椎の歪み → 椎骨動脈の圧迫
頭蓋骨の緊張 → 静脈・リンパの滞り
胸郭の硬さ → 全身の循環不良
これらの構造的制限を解除し、血液・リンパが自由に流れる状態を取り戻します。
2. 神経の過敏化を「沈静化」
体性感覚(首や顎からの信号)が聴覚系と混線すると、耳鳴りは悪化しやすくなってしまいます。
頸椎・頭蓋の微細な調整で神経圧迫を軽減し硬膜の張力を整え、脳幹への負荷を減少させることで自律神経のバランスを回復し結果として、過敏化した神経システムを落ち着かせることができます。
3. 「全身のつながり」を調和させる
耳鳴りは、遠く離れた骨盤や腰椎の歪みが原因になることもあります。
骨盤の傾き → 脊柱全体の連鎖 → 頸椎への負担
筋膜の緊張 → 後頭部・側頭骨への影響
呼吸の浅さ → 胸郭の硬さ → 頭部への血流低下
局所だけでなく、身体全体のバランスを調和させることで、根本から耳鳴りが起こりにくい状態を作ります。
耳鳴り改善の重要ポイント
頸椎・頭蓋骨の調整
最も重要な施術ポイントとして
耳鳴りと最も関係が深いのが、上位頸椎と呼ばれる頚椎1〜3番と頭蓋骨。
環椎(C1)軸椎(C2)の微細な調整をおこなうことで椎骨動脈の圧迫を解除し、内耳への血流を改善し
、後頭骨と側頭骨の可動性回復することで側頭骨のわずかな緊張やズレを調整しことで、内耳のリンパ圧・神経伝達を正常化します。
顎関節・咀嚼筋の調整
「噛みしめ」「食いしばり」が耳鳴りを作る
咬筋・側頭筋・外側翼突筋のリリース
過緊張した咀嚼筋をゆるめ、顎関節への負荷を軽減
下顎骨の位置調整
左右の噛み合わせバランスを整え、側頭骨への影響を改善
胸椎・胸郭・骨盤の調整
「土台」が整わなければ、頭部も整わない
頸椎の問題は、その下の胸椎・骨盤の歪みから生まれることが多くありますので
猫背や側弯といった脊柱の歪みを整え、頸椎への負担を軽減します。
骨盤の傾き・回旋の調整し骨盤が整うことで脊柱全体のバランスを回復させ、頸椎と頭蓋への負荷が減少させるとともに、硬膜管の下端に付着している仙骨と硬膜の調整で脳幹・頭蓋への膜の張力を安定させて耳鳴りの改善に導きます。