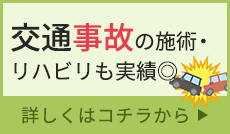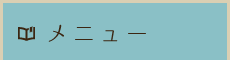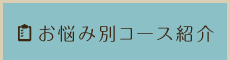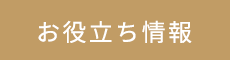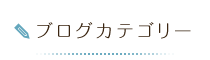産後の体は自然には戻らない?今知っておきたい骨盤ケアの基本
出産を終えたあとの体は、思っていたよりも身体の変化が大きくないですか?
- 出産後から尾てい骨が痛い
- 骨盤が開いたままで、歩くときに違和感がある
- 尿漏れが気になって、外出が億劫になった
- 体重は戻ったけど、お腹のたるみが気になる
そんな変化を感じながらも、日々の多忙な生活に追われていつの間にか身体の不調が大きくなってきていませんか?
実は、産後の体は自然に元の状態まで戻らないことが多く、脊柱や骨盤の歪みをそのまま放っておくと、後々の痛みの原因や身体の歪みのクセとなって残ってしまいます。
この記事では、なぜ産後に骨盤が歪むのか、そして、どのように整えていくと根本から改善できるのかを分かりやすくお伝えしていきます。
産後の骨盤はどう変化するのか?
まず結論を言うと 出産前後で骨盤は形も支え方も変化し、結果として安定性が低下重心バランスが崩れることで、さまざまな部位に負担がかかることに繋がります。
骨盤のリング構造?立つ・歩く・抱っこを支える骨盤の特殊構造
骨盤と呼ばれるものは左右の寛骨と呼ばれる骨と、後ろの仙骨でできる「環状(リング)構造」で前側は恥骨と恥骨で構成される恥骨結合、後ろは仙と寛骨で形成される仙腸関節でつながっています。
この真ん中が空洞で、リング状になっておる骨盤構造は主に2つの安定化要素で成り立っており
骨同士のかみ合わせによる形態的支持と靭帯の力学的支持でリング状という特殊な構造であっても強固に連結しながらも可動性を維持できているのです。
形態的支持
骨盤の安定性は、筋肉や靭帯の力だけでなく、骨同士の形状によるかみ合わせでも支えられています。これを形態的支持と呼びリング状に連結することで、立位や歩行時に体重を分散しやすくなっています。
前は「恥骨結合」 後は「仙腸関節」で連結され
恥骨結合は左右の恥骨が軟骨で連結し。多少の可動性はありますが強固なかみ合わせで骨盤の前方を安定させています。また後方の仙腸関節は仙骨と腸骨が複雑にかみ合い、ねじれや衝撃を受けても安定する特殊構造で、関節面の凹凸で自然に骨がずれにくくなっています。
形態的支持に問題が起きると?
出産や外傷で骨盤の形状やかみ合わせが微妙に変わると、骨盤全体の安定性が低下靭帯や筋肉に負荷が集中し、腰・尾骨・股関節に痛みや不安定感が出やすくなります
力学的支持
骨盤は骨同士のかみ合わせだけでなく、靭帯や筋肉の張力といった骨盤の外から締める力で支えられています。力学的指示の役割を行う主な靭帯としては
仙腸靭帯
この靭帯は仙骨と腸骨をつなぎ、骨盤後方を支えるベルトのような働きをし、産後の緩みが尾骨痛やお尻の不安定感の原因に。
恥骨結合靭帯
左右の恥骨を前でつなぎ、骨盤前方を安定。出産で開きすぎると歩行や立位で痛みやぐらつきが出やすくなります。
仙結節・仙棘靭帯
骨盤の後下方を支え、ねじれや衝撃を吸収し緩むと尾骨や腰の痛みの原因に。
これらの主要靭帯が緩んでしまうと骨盤が不安定になり、腰・尾骨・股関節に負担が集中しやすくなり、常に筋肉が緊張することで痛みや姿勢のクセが出やすくなる
出産で骨盤がゆるむ理由「リラキシン」が体に与える影響
ホルモンでゆるむ靭帯と骨盤の不安定
妊娠〜出産期には、リラキシンをはじめとするホルモンが増加します。このホルモンの作用で、靭帯や結合組織が柔らかくなり、骨盤の可動性が増すのです。
妊娠出産に関するホルモンの詳細はこちら
▼▼▼
ホルモンの影響を受けやすい靭帯として最も影響を受けやすいのが
骨盤前方の恥骨をつなぐ靭帯の恥骨結合靭帯
これがゆるむことで骨盤の前側が柔らかくなり、歩行時や立ち上がりで痛みを感じることがあります。
次は仙骨と腸骨をつなぐ後方の仙腸靭帯
太く強力な靭帯ですが、リラキシンの影響で弛緩し、仙腸関節の安定性が低下。お尻〜腰の痛みや尾骨痛の原因になります。
あと、じつは靭帯に限らず骨盤底筋を中心とした関連結合組織も同様で
骨盤底の筋肉・靭帯も柔らかくなり、支持力が弱まり、尿失禁や恥骨・尾骨周囲の違和感の要因になることがあります。
当然ながら骨盤リングの安定性への影響も大きく
前側の恥骨結合と後ろの仙腸関節のす靭帯のゆるみにより、このリング構造の安定性が低下し結果として、立つ・歩く・抱っこするなど日常動作で骨盤に不均等な力がかかりやすくなります。
回復の目安と個人差
ホルモン分泌の正常位によって出産後、靭帯は自然に徐々に硬さを取り戻すことが多く
一般的には栗肉などでは産後6か月程度で安定することが多いと言われますが、実際の回復のスピードや程度には個人差があり
この、産後も靭帯のゆるみによる骨盤や脊柱のズレや歪みが残ることで、産後の数々の変化を身体にもたらします
妊娠中の重心と産後のクセ|前傾姿勢が腰痛を招く仕組み
マタニティ期には、妊娠に伴う体重増加と、子宮の前方突出により 重心が前方へ移動します。この重心移動に適応するために
腰椎が前弯し腰が反り、それとともに骨盤の前傾も強まり、腰への前方負荷が増えます。
この腰椎の前弯が強くなった腰が沿った状態は、歩行時の骨盤の前に回旋する傾きが大きくなり、仙腸関節や恥骨結合へのずれる力や回旋力が増加することで、様々な不調を引き起こすのですが
産後はこの重心変化や姿勢のクセが残りやすく、骨盤周囲のな負担が継続します。
出産の瞬間、骨盤には何が起こっているのか?
分娩時、胎児が骨盤を通過することで恥骨結合や仙骨周囲に強い力がかかることがあり
その結果として恥骨間に過度の開大が生じることがあり、それによって恥骨結合の過度の拡大が起こりることで恥骨前方の痛みや歩行時の困難を招く原因に。
また「長時間にわたる難産」や「器械による吸引分娩」などで
尾骨の過伸展などで仙骨〜尾骨への損傷が起こる場合があり。これが尾底骨痛の原因そのものになることがあります。
また帝王切開で分娩した場合でも、妊娠期間のホルモンや体重・姿勢変化の影響は残るため、骨盤関連の問題は、自然分娩と同様に発症します。
腹筋・骨盤底筋・臀筋群の3つの支持する筋肉
出産後の体では、骨盤を中心とした構造の変化とともに、骨盤を安定させる筋肉のバランスも大きく変化します。特に妊娠・出産に伴う筋肉の伸張や負担によって、「骨盤を締める作用をする筋肉群の筋力は低下しやすくなります
腹横筋
腹横筋は身体のコルセットのような役割で妊娠中にお腹が大きくなると伸ばされ、出産後も働きが弱まりがち。弱くなるとお腹がぽっこりしたり、姿勢の崩れにつながります。
骨盤底筋群
骨盤の底にハンモックのように広がる筋肉で出産時に強く伸ばされ、筋力低下や感覚の鈍りが起こる。支えが弱くなることで、尿漏れ・恥骨や尾骨の不快感・内臓下垂などの原因に。
殿筋群(特に大殿筋・中殿筋)
基本的には立つ・歩く・骨盤を安定させる主要筋。妊娠中は活動量の低下や姿勢変化で使われにくくなり、出産後に筋力が落ちやすく弱くなると、お尻が垂れてきやすくなったり股関節痛が起こりやすいのが特徴
痛みが長引くのは神経が過敏
出産後の体では、骨盤や筋肉の変化だけでなく、神経系のバランスにも大きな影響が出ます。
女性は出産すれば終わり。でなく出産してからも、その身体の変化は続きます
- 睡眠不足やホルモンバランスの変化
- 抱っこや授乳による長時間の姿勢不慮と負担の増大
これらが続くことで、産後、身体が修復するステージに入っていても
脳や神経が「痛みを覚えてしまう」勘作という状態に移行することがあります。
すると、出産時の傷んでいたところの痛みが残る。軽い刺激や姿勢の変化で痛みを感じやすくなる・慢性的な尾てい骨痛・腰痛・恥骨の違和感が続く。といった状態が起こります。
特に、骨盤のゆがみや姿勢の崩れが続くと、仙腸関節や坐骨神経の通り道を圧迫・刺激して、脚への放散痛やしびれにつながることもあります。
妊娠から産後の流れ

【妊娠期】
徐々にホルモン分泌が亢進することで重心は前方シフトし腰椎前弯が増大
【分娩直後】
靭帯が弛緩した状態と、分娩時の外力 → 分娩数日以内は分娩時の痛みが主
【短期回復期】
多くは徐々に回復傾向に向かってくる時期で、身体は回復してくるじきですが
生後1~3ヶ月は育児による睡眠不足などのストレスも多く、痛みや不調を強く引き起こすケースも多い時期です。
【中長期】
だんだんと靭帯などの軟部組織の硬さが正常化してくる時期です、このタイミングで姿勢のクセが定着したり、分娩時の損傷などで慢性痛が長引く人も。
痛みは「骨盤だけ」が原因ではない複合メカニズム
実は、産後の腰痛・尾てい骨痛は骨盤単体のズレだけで説明できません。
骨盤を中心に、姿勢・筋肉・関節・神経・心身が複合して影響を出します
重心バランス・姿勢アライメントの変化
妊娠から出産で重心が前方へ移動した姿勢のクセが残り、継続して骨盤に偏ったストレスが続くと、腰や尾てい骨に痛みが出やすくなります。
関節連鎖の問題
授乳や抱っこによるゆがみによって起こる関節連動不良で股関節・膝・足首、脊柱の可動性が落ちると、その代償が骨盤に集中しやすくなります。
たとえば股関節の内旋制限や片側重心があると、骨盤の位置異常がに元に戻らず歪んだままで痛みの原因となります。
循環の不慮による神経系の異常
姿勢や骨盤周囲の筋緊張で坐骨神経・陰部神経が刺激されると、しびれや鋭い痛みが出ることがあります。妊娠中の脊柱の歪みからくる静脈うっ滞・リンパ滞留などの循環不慮は産後も継続して鈍痛や重だるさを訴えることがあります。
心理的な痛み感受性の上昇
睡眠不足・育児ストレスは自律神経の乱れを招き、持続的な交感神経亢進による痛みの感受性(感作)を高めます。こういった感作による影響で構造的な異常が小さくても「痛みが長引く」原因の1つになります。
さくら整骨院ではどのように全身を整えていくのか?
多くの方が「骨盤矯正」という言葉を聞くと、
骨盤の位置を「グッと動かす」ような施術を想像されるかもしれません。
しかし、実際の身体の仕組みはもっと繊細で、
「骨盤だけを動かせば良い」というものではなく、さくらら整骨院では、骨盤を含めた全身の構造バランスを重視し、痛みの根本原因にアプローチしていきます。
骨盤を「整える」だけでなく「支える力」を回復させる
骨盤のゆがみやズレを起こしている本当の原因は、
骨そのものではなく、それを支えている脊柱・骨盤・神経のバランスです。
妊娠・出産でリラキシンというホルモンが分泌され、骨盤周囲の靭帯は一時的に柔らかくなります。出産後、その靭帯が再び元の硬さに戻っていく過程で、
正しい位置で安定できなければ「ゆがみ」として固定されてしまいます。
当院では、骨盤を一時的に“矯正する”のではなく、
その支えとなる脊柱。骨盤と神経機能の働きを回復させることを目的としています。
これにより、外から形を整えるのではなく、身体の内側から正しい位置を保てる状態を作ります。
背骨・股関節・肩甲帯など「全身の連動性」を調整
骨盤は単体では動けません。
たとえば、
股関節の動きが悪いと骨盤がねじれて動き
脊柱の可動性が失われるとで過度に骨盤の可動性が求められます
また肩甲骨と脊柱の動きの偏りが骨盤の傾きを生むというように
全身は常に円滑な連動性で動いています。
さくら整骨院では、骨盤だけでなく背骨・股関節・肩甲帯・などの連動機構を細かく評価し
動きのズレや硬さをひとつずつ整え調整していきます。
これにより、身体全体のバランスと調和が自然に取れ、
「立つ」「歩く」「抱っこする」といった動作の円滑さが格段に向上し
身体の健康状態を維持しやすくなるのです。
構造医学的アプローチにより神経・循環の通り道を整える
体の痛みは、筋肉や骨格だけでなく神経の伝達障害によっても生じます。
出産による骨盤の開きや姿勢の変化で、
坐骨神経・大腿神経・陰部神経などが軽度に圧迫されると、腰・尾てい骨・太ももなどに鈍痛や違和感が現れやすくなります。
当院では、構造医学の理論に基づき神経の滑走性が回復することで
関節や脊柱の働きも自然と改善し、痛みが再発しにくい体へと変わっていきます。
産後ケアはいつから始めるのがベスト?
リラキシンと回復時期の関係
出産後の骨盤ケアを考えるとき、「いつから始めればいいですか?」とご質問をお受けします。
早すぎても体に負担がかかりそうだし…
遅くなると戻りにくくなる気がする…
など
ここでは、産後の体の中で何が起きているのかを詳しくお伝えしています。
出産後、骨盤の靭帯はまだ「柔らかい」
妊娠中から出産直前にかけて、女性の体では
骨盤や恥骨結合・仙腸関節といった靭帯を柔らかくし、
赤ちゃんがスムーズに産道を通れるようにする働ために
リラキシンというホルモンが多く分泌されますので
「骨盤を一時的に大きくゆるめている状態」です。
リラキシンの分泌は産後もしばらく続く
出産後、リラキシンの分泌量は少しずつ減少しますが、
完全に元の状態に戻るまでは約6か月程度かかるとされています。
この間、靭帯はまだ柔らかく、骨盤が安定しにくい状態です。
そのため、この時期には「無理な運動」や「無理な矯正」を行うと、かえって負担をかけてしまうこともあります。
当然ながら、無理な矯正というのは産後でなくても
「無理に行ってはいけない」ですが
産後の矯正や整体の場合は
通常の感覚とは、明らかに違う硬さの身体になりますので
産後の柔らかくなった身体にあわせた施術を行ってもらうことで
骨盤は「より自然に正常な位置」に戻りやすくなります。
産後ケアを始める目安
一般的には
産後1か月頃が安全なスタート時期でといわれています。
これは、分娩時に身体の中からおおきな負担がかり激しい痛みとともに出産をしていますので
ダメージをおった細胞を安静に療養させてあげる。という観点から
1ヶ月頃が安全だとされます。
この時期には、体の回復も少しずつ進んではいますが
授乳や寝不足などで、痛みや不調を感じる方が増えますので
精神的にも、身体的にも身体を整えていくことで
大変な育児生活をより快適に健康的に過ごすことができるでしょう。
最も効果的な時期は「あなたの体が整う準備ができた時」
産後6か月を過ぎても遅くはない
「もう6か月以上経っているから手遅れですか?」
という質問を受けることもありますが
基本的に、いつのタイミングであっても遅いことはありません。
確かにリラキシンの影響で靭帯が柔らかい期間は効果的ではありますが
実際では10年以上経ってから、出産のあとから腰がいたかったのですが、なかなか忙しくて・・・と言われて来院される方も多くいらっしゃいます。
ですから、リラキシンの分泌時期は、あくまで目安くらいに考え
ご自身が「改善したい」と思われたタイミングが最善のタイミングだと思われるとよいでしょう。