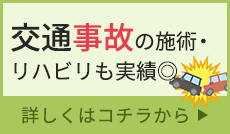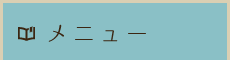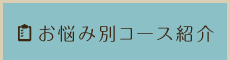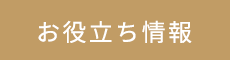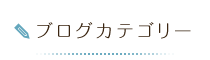岡山の脊柱管狭窄症治療 | 岡山駅徒歩5分のさくら整骨院
「長く歩くと脚がしびれて歩けなくなる」
「腰を反らすと腰や足に痛みが走る」
「座って休むと楽になるけれど、立つとまた痛みが出る」
そんな脊柱管狭窄症にお悩みではありませんか?
脊柱管狭窄症って?
脊柱管狭窄症は、単なる加齢や骨の狭小化だけで起こるものではありません。
「腰椎や骨盤の歪み」「椎間関節の変形」「周囲の筋肉や筋膜の緊張」
「姿勢の崩れや長年の疲労の蓄積」が関与し、神経の通り道である脊柱管が圧迫されることで脚や腰に痛みやしびれを生じます。
脊柱管狭窄症を本気で改善したい方へ
専門家による根本的な施術で、歩行や立位でのしびれや痛みを軽減し、日常生活を快適に取り戻すしていきませんか?
神経が通るトンネルが狭くなるの脊柱管狭窄症
脊柱管とは?
背骨が縦に並ぶことで形成される、神経の通り道(トンネル)のことで
その中に、脊髄や馬尾神経、神経根、血管などが走行しているのですが
加齢や姿勢・動作のクセによって
下記のような構造的変化が起こると、管の空洞が少しずつ狭くなってきます。
- 椎間板が加齢で潰れて後方に膨らむ
- 背骨の後ろの椎間関節が変形して肥厚する
- 黄色靭帯が分厚く硬くなる → 肥厚、石灰化
- 骨が刺激でトゲのように増える:骨棘形成
これらが組み合わさって神経・血管の通り道を圧迫するのですが
この「狭さ」そのものが痛みを出すのではなく狭窄されたことによって
神経に対する「圧迫」+「血流障害」+「浮腫」が起こることで神経の伝達障害が起こることが根本的な問題で
時として、椎体がずれて「すべり症」を合併することもあります。
姿勢によって症状が変わる
脊柱管狭窄症の最大の特徴は、「姿勢によって症状が変わる」こと。
-
腰を反らす(伸展姿勢)と症状悪化
→ 神経がさらに圧迫され、血流が減る -
前かがみ(屈曲姿勢)になると症状軽快
→ 神経管が少し広がり、血流が回復
このため
「立っていると脚がしびれるけど、自転車なら平気」
「買い物カートを押すと楽に歩ける」
といった訴えが非常に多くみられます。
これは、神経圧迫の血流性変化が強く関係しており
単なる神経の物理的な圧迫だけでは説明できないのが特徴です。
一般的な腰痛との違い
| 一般的な腰痛 | 脊柱管狭窄症 | |
|---|---|---|
| 原因 | 筋肉・靭帯の炎症 | 神経、血管の圧迫 |
| 姿勢変化 | 動くと痛い(特に前屈) | 反ると悪化、前かがみで楽 |
| 痛みの部位 | 腰中心 |
腰〜脚 (片側または両側) |
| しびれ | ほぼなし | 坐骨神経領域 |
| 歩行距離 | 問題ない | 一定距離で限界 → 間欠性跛行 |
脊柱管狭窄症の初期
神経の軽度圧迫・血流障害
歩行時にふくらはぎ〜足先にジンジン感
朝は平気でも、午後〜夕方になると悪化
→ この段階では、姿勢性・時間性の変化が特徴で
血流の循環が悪くなることで一時的な神経虚血が起きるためです。
脊柱管狭窄症の中期
神経根への圧迫が強くなる
→ 数百メートル歩くと脚がしびれて動けなくなるという間欠性跛行が明確になり
しゃがむとすぐ回復するという段階
足先の感覚が鈍かったり、冷たい感じがすることや、力が入りにくい、足がもつれるといった症状で両側の脚に症状が出ることもあります。
この時期から「神経の伝達障害」と「血行障害」が進行し、
感覚や運動機能の低下がみられ始めます。
脊柱管狭窄症の中期
馬尾神経障害
神経の最下部である「馬尾神経」が圧迫されると、より重篤な症状が現れます。
症状としては
- ジンジン・ピリピリとした両脚の感覚鈍麻
- 力が入らず、つまづきやすくなる
- 排尿・排便トラブルといった膀胱直腸障害
- 尿が出にくい・残尿感・尿漏れ・失禁など
これは神経機能の「麻痺段階」に入りつつある状態で
この段階では手術的除圧が必要とされることもあり
長く放置してしまうと後遺症が残る可能性もでてきます。状の出方の3つのパターン
①神経根型「片脚症状が主体」
腰から片脚に痛み・しびれが走り
動作で一側にズキッとくる、神経の根元が圧迫されているタイプ
② 馬尾型「両脚・下半身の脱力や排尿障害」
両脚が重だるさや、ジンジンすることや、感覚が鈍くなることもあり
尿や便のコントロールがしにくくなることもあるタイプ
③混合型「上記の両方を併発」
神経根の痛みと馬尾の血流障害が混在し中高年で多くみられ、症状が複雑に入り混じるタイプ
症状が強く出やすい動作
| 動作 | 症状の変化 |
|---|---|
| 立つ・腰を反らす | 悪化 → 神経圧迫・血流低下 |
| 歩く | 徐々にしびれや痛み増強 |
| 座る・前かがみ | 改善 → 神経が解放される |
| 自転車・前傾の家事姿勢 | 比較的楽 |
| 寝返り・仰向け寝 | 時に悪化 → 腰椎伸展方向 |
【生理学的に見た症状の背景】
→ 脊柱管が狭くなることで、神経を包む「硬膜外腔」の血流が減少し
神経根の虚血が起こります
→ 神経は酸素不足に弱く、数分の虚血でも神経伝導速度が低下し
歩行中は下肢筋の収縮で静脈還流が変化し、圧力が上がるためさらに虚血が進行
→ 前屈すると脊柱管が拡がり、血流が回復すれば → 症状が軽快。
これが間欠性跛行のメカニズムです。
脊柱管狭窄症の生理学的メカニズム
構造的変化からの「神経」「血管」の圧迫
脊柱管は、椎骨の後方にある「椎弓」と前方の「椎体」、その間の「椎間板」で囲まれた神経のトンネルでその中を「脊髄・馬尾神経」「神経根」「血管(動脈・静脈)」が走行しています。
加齢や慢性的な力学的ストレスによって
- 椎間関節の変形・骨棘形成 → 後方から狭窄
- 椎間板の脱水・扁平化 → 後方膨隆
- 黄色靭帯の肥厚・硬化 → 後方から圧迫
- 椎体の変形・すべり症 → 前後方向のズレ
これらが複合的に起こり、神経や血管を圧迫する環境が形成されます。
ここまでは構造的な「狭窄」ですが
実際に症状を引き起こすのは循環・神経伝導・炎症といった生理学的変化です。
虚血による神経機能低下
神経組織は非常に血流依存性が高い組織です。
神経根や馬尾神経に栄養運ぶ神経根動脈、静脈叢と呼ばれる血管は
脊柱管内を通過し
動脈が圧迫されることで → 虚血による酸素供給の低下が起こり
静脈が圧迫されることで → うっ血・浮腫が起こります
神経は虚血に非常に弱く
数分〜数十分の血流低下で伝導速度が低下し、疼痛やしびれが出現します。
これが「歩くと痛くなり」、「前かがみで楽になる」間欠性跛行の根本的メカニズムです。
前かがみ姿勢では脊柱管の断面積が約13〜30%広がるとされ
硬膜外腔の静脈圧が低下することで → 血流が回復 → 神経の伝達が改善します。
神経浮腫と炎症による二次障害
慢性的な狭窄が続くと、神経根周囲では慢性炎症性浮腫が起こります。
これは
圧迫による局所虚血 → 血管透過性が亢進
血漿成分の漏出 → 神経周囲に浮腫
浮腫がさらに圧迫を助長する → 悪循環
この慢性炎症環境では
神経内でサイトカインやプロスタグランジンが増加し
神経の閾値が下がり軽い刺激でも痛みを感じる
神経過敏状態になります。
また、浮腫によって神経に対する栄養の流れが阻害され、
末梢側の神経線維変性(ワーラー変性)や脱髄が進行することもあります。
機械的ストレスと神経伝導の関係
脊椎は動く構造体と呼ばれ
腰椎は伸展(反る動き)で脊柱管が物理的に狭くなります。
腰椎伸展 → 椎弓が前方に倒れ、脊柱管の前後径が減少
黄色靭帯が内側へ膨隆 → 馬尾神経の圧迫が増加
屈曲 → 椎弓が開き、黄色靭帯が後方へ引かれ管が拡大
MRIで測定すると腰椎の伸展時には脊柱管面積が最大40%狭くなるとされることもあります。
馬尾神経
腰椎下部では、脊髄が終わり「馬尾神経」という束状の神経群に移行します。
この馬尾は硬膜嚢の中で比較的自由に動く構造ですが、狭窄が進行すると
- 馬尾神経の周囲静脈叢がうっ血し、硬膜内圧上昇
- 神経線維間の滑走障害(癒着)
- 神経栄養の低下による軸索変性・脱髄
結果として
両下肢のしびれ・感覚鈍麻・排尿障害などが出現します。
この段階では単なる「痛み」ではなく神経機能そのものの障害です。
自律神経系への影響
馬尾神経や仙髄神経には、交感神経・副交感神経線維が含まれます。
そのため、圧迫が進むと
- 膀胱・直腸のコントロール障害(排尿・排便トラブル)
- 下肢の冷感・血流障害(交感神経緊張の偏り)
これらは神経根の局所炎症だけでなく、脊髄下部の自律神経核への循環低下が関与していると考えられています。
なぜ慢性化するのか?
長期的に神経の虚血・圧迫が続くと
末梢神経だけでなく中枢神経(脳・脊髄)の可塑性変化が起こります。
慢性刺激により脊髄後角の痛覚ニューロン感受性が上昇し
脳内での痛覚抑制系の機能は低下
結果、実際の圧迫が軽くても痛みが残る
慢性疼痛化
が起こるメカニズムで
これが「手術後も痛みが残る」例で
単に構造を広げるだけでは不十分な理由でもあります。
整体やリハビリでは、この神経の過敏化・感覚統合の回復を目的に
アプローチすることが重要となってきます。
脊柱管狭窄症の生理学的連鎖
構造的狭窄(骨・靭帯・椎間板変性)
↓
神経・血管の圧迫
↓
虚血+うっ血・浮腫
↓
神経伝導低下 → 「しびれ」「脱力」「疼痛」
↓
慢性炎症・軸索変性 → 「神経過敏化」
↓
慢性疼痛このように、「狭い」という形の問題が
時間とともに「神経生理の障害」へと発展していくのが脊柱管狭窄症の特徴。
生理学的アプローチ
整体では「骨を矯正する」だけでなく、循環・神経伝達・滑走性を改善するアプローチが有効になります。
- 骨盤・腰椎のアライメント調整 → 硬膜張力を緩める
- 胸腰移行部・仙腸関節の可動性回復 → 血流改善
- 呼吸性運動(横隔膜リリース) → 硬膜管内圧を調整
- 交感神経の過緊張を抑える → 血管拡張・虚血軽減
これにより、「構造の狭さ」ではなく「神経の生理的環境」を整えることが、
保存的改善をめざす上でのキーポイントになります。
腰椎周囲の脊柱支持筋の役割
脊柱起立筋・多裂筋
背骨を支え、姿勢を維持する役割が中心。
加齢や痛みにより筋力低下 し背骨の支持力不足脊柱の微細なズレを助長することで
椎間関節・黄色靭帯への負担が増し脊柱管狭窄の症状を進行させます。
腹横筋
腹横筋は腹圧を高めて腰椎を安定させます
この筋肉が弱化すると
腹圧不足すると、腰椎伸展時に椎間板後方への負荷が増加することで神経管の圧迫を助長するので体幹深層筋を強化することで、前かがみでなくても神経管の圧迫を軽減可能になります。
大殿筋・中殿筋
股関節の安定と歩行サポートするのが中心で
弱化すると歩行時に腰椎伸展が増え症状悪化の原因となり
坐骨神経への二次的ストレス増えることで、さらに神経症状を強めます。
関節の可動性と脊柱管の圧迫
椎間関節
腰椎の後方にある小さな関節で、椎間関節は背骨の動きを制御するのですが
加齢と共に変形が起こりやすいところで
関節面の変形・骨棘形成 → 神経根を圧迫
関節硬直 → 腰椎伸展時に狭窄が強くなる
ただ、どちらの場合であっても可動性を改善することで
脊柱管の物理的圧迫を軽減可能です。
仙腸関節
仙腸関節は骨盤と脊柱をつなぐ関節で、可動性が低下することで
腰椎全体の伸展・回旋が制限され 歩行時に腰椎の負担が増加し
→ 間欠性跛行の原因に
筋膜・靭帯の視点
黄色靭帯
脊柱管後方を覆う比較的柔軟性の高い靭帯で
加齢によって肥厚・硬化し神経圧迫の主因で
黄色靭帯に隣接する「脊柱起立筋」や「多裂筋」の緊張が
靭帯圧迫をさらに助長しヘルニアの症状を強める原因になります。
腰方形筋・腸腰筋
腰椎を側屈・前屈させる筋肉で、緊張が強いと腰椎の伸展を助長し神経管を圧迫させ
逆に前屈で症状が楽になる理由の一部は、この筋肉の伸張による硬膜管の開放をするもので
マッサージなどで、一時的に緩和するケースもこの骨格筋の影響があります。
筋肉・関節からみた症状メカニズム
歩行時に脚がしびれる
→ 臀筋・多裂筋の筋緊張 → 腰椎伸展が増 → 神経管圧迫
座ると楽になる
→ 腰椎屈曲、腸腰筋や多裂筋が伸張 → 脊柱管の断面積拡大
前かがみで楽になる
→ 腹横筋・深部背筋が緩み、椎間関節後方の圧迫減少
慢性的な腰痛・張り感
→ 筋肉が防御的に硬直 → 関節の可動性が減 → 圧迫が持続 → 痛み悪循環
脊柱管狭窄症は 「骨だけの問題ではなく、筋肉・靭帯・関節の連動異常」 が症状に直結します。
脊柱管狭窄症に対するアプローチ
骨・関節に対するアプローチ
【椎間関節のモビリゼーション】
狭窄部の椎間関節や隣接関節の可動性低下を検査で評価して、微妙な関節運動を導入して関節面の滑走を改善することで「神経根圧迫の軽減」「周囲筋の過緊張緩和」を図ります。
【仙腸関節・骨盤の調整】
仙腸関節の硬直は腰椎全体の伸展ストレスを増加させる為
関節可動性を回復させることで腰椎下部の脊柱管圧迫を緩和
硬膜・神経滑走に対するアプローチ
硬膜(脊髄を包む膜)の張力やねじれをを改善することで
脊柱管の神経空間を改善し血流障害や神経虚血の軽減するとともに神経伝導の回復を図ります。
特に馬尾神経・神経根の滑走性改善は、間欠性跛行や下肢しびれの改善には非常に重要です。
神経・血管循環の調整
脊柱管狭窄による神経虚血を解消するため、全身的な循環調整も実施
骨盤・胸椎・横隔膜周囲の動きを改善 → 硬膜内圧を間接的に緩和
血流・リンパ循環の改善 → 神経浮腫の軽減
このアプローチにより、神経根・馬尾神経の酸素・栄養供給を促進し、症状改善を目指す
アプローチの原則
①構造の微細な調整
→ 強く押すのではなく、骨・関節・筋膜の張力バランスを最適化
②機能を優先した調整
→ 動きや循環が改善することが治療目標
③神経滑走の確保
→ 神経が自由に動ける環境を作る
④循環と代謝の改善
→ 局所の血流改善 → 虚血・浮腫・炎症の軽減
脊柱の正常アライメント
腰椎・胸椎・頸椎の生理的彎曲の役割としては
- 荷重分散:背骨の湾曲が衝撃を吸収
- 神経保護:神経や馬尾の通り道(脊柱管)を広く保持
- 可動性確保:前屈・後屈・回旋などの運動をスムーズにする
があり、正常では「腰椎は軽度前弯」「胸椎は軽度後弯」「頸椎は前弯」のS字カーブを描きます。
歪みが症状に与える影響
脊柱の歪みによる影響は大きく分けて3つ
① 構造的圧迫の悪化:椎間孔や脊柱管の断面積が局所的に狭くなることで神経根・馬尾神経への物理的圧迫が増加
② 筋肉・筋膜の不均衡:片側の筋肉に過剰な負荷がかあkることで脊柱のさらなる歪み多裂筋・脊柱起立筋・腸腰筋の硬直を引き起こし姿勢依存性の症状を悪化させます
③ 血流・神経滑走障害:神経・硬膜の引き伸ばしや圧迫血管循環の障害 で、神経虚血・浮腫をまねきしびれ・間欠性跛行を誘発します
歪みの改善で期待できる効果
- 間欠性跛行の軽減 → 歩行距離が延びる
- 片側下肢のしびれ・痛みの改善
- 筋肉の過緊張緩和 → 神経圧迫の悪循環解消
脊柱の歪みは「神経圧迫」「筋肉・筋膜の硬直」「血流障害」の三重構造で症状を作ります。
そのため、単に骨を整えるだけでなく、全体の連動を整えることで改善の難しい神経根の症状を改善することができるのです。