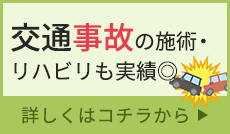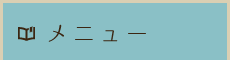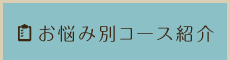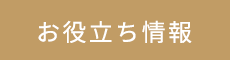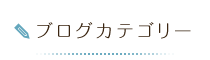岡山の腰椎分離症・すべり症治療 | 岡山駅徒歩5分のさくら整骨院
腰を反らすと痛い、長く立っていると腰が重い
スポーツ中に違和感が出る、動き始めにズキッと痛む
それは「腰椎分離症」や「腰椎すべり症」が原因かもしれません。
生理学的な構造と機能に基づいた施術を行うさくら整骨院では、
痛みのある部位だけでなく、体幹の安定性・骨盤のバランス・下肢の支持性・脊柱の可動性を総合的に評価。全身の運動連鎖を整えることで、再発しにくい強い腰をつくります。
岡山で腰椎分離症・すべり症のつらい症状を改善したい方へ
痛みを気にせず動ける、軽やかな身体を取り戻しましょう。
腰椎分離症・すべり症とは
ある日突然
「腰を反らしたときにピキッと痛んだ」経験はありませんか?
腰椎分離症は、腰椎の後方にある椎弓(ついきゅう)と呼ばれる部分が
繰り返しのストレスによって疲労骨折を起こす状態で
分離した腰椎が、徐々に前方へ滑り出してしまうのが「腰椎すべり症」
分離症を放置したり、姿勢や体幹バランスが崩れたまま生活を続けてしまうと
すべり症へと進行するケースが比較的多く見られます。
分離症とすべり症の発生機序
腰椎の椎弓峡部は、椎体と椎弓をつなぐ「細い橋のような構造」となっています。
この部位は「腰を反らしたり」「ひねった時」による負担が集中します。
この繰り返しの小さなストレスによって、骨に対する微細損傷が重なり → 疲労骨折(分離)を起こします。
これが後に2つある細い橋が両側断裂すると、椎体が前方へ滑るようになる状態を
分離すべり症と呼び、発生部位は約85〜95%が第5腰椎で、次いで第4腰椎が多くみられます。
すべりの分類
椎体がどの程度前方へ移動したかを%で評価を行い
-
Ⅰ度:25%以下
-
Ⅱ度:25–50%
-
Ⅲ度:50–75%
-
Ⅳ度:75%以上
レベル4すべり症では、椎体のすべる範囲も大きいので
神経根圧迫や脊柱管狭窄を合併することもあります。
特徴
一般成人の約4〜6%には、痛みがない無症状でも分離が見られ
10〜17歳の成長期のスポーツ選手は発症率が高い傾向にあり
成長期アスリートでは無症状もふくめ、10〜20%と高率で発症すると言われます。
進行の流れとしては
-
ストレス反応期 → 骨内浮腫が起こり
-
疲労骨折期→明らかな裂離が生じる
-
偽関節化 → 骨癒合せず慢性化
-
すべり症移行期 → 両側性欠損 することで椎体前方移動
という流れで、分離症からすべり症へと移行していきます。
腰椎分離症
腰の中央や片側の鈍い痛みがあり、腰を反らしたり、スイングなどで痛みが強くなり
基本的には安静や前屈で一時症状が軽快する傾向です。
腰椎すべり症
腰痛に加えて、下肢のしびれ・だるさを併発する場合があり、長時間立位や歩行で症状増悪する、神経性間欠跛行と呼ばれる症状を引き起こすこともあり。
高度例では神経根などに影響して下肢筋力低下や知覚障害を起こす場合もあります。
すべり症の中で鑑別が必要となるのが「変性すべり症」
変性すべり症との違い
| 項目 | 分離すべり症 | 変性すべり症 |
|---|---|---|
| 原因 | 椎弓の分離(疲労骨折) | 椎間板・椎間関節の退行変性 |
| 年齢 | 若年〜中年 | 中高年女性に多い |
| 好発椎 | L5 | L4 |
| 神経症状 | 進行例で出現 | 高頻度で出現 |
腰椎分離症・すべり症の生理学的メカニズム
骨と関節への負荷と疲労骨折
腰椎分離症は椎弓が反復的なストレス、特に腰の過伸展にさらされることで微小骨折を起こす状態で、骨は骨形成と骨吸収のバランスで維持されるのですが
成長期や過負荷の際には骨吸収が追いつかず亀裂が生じ関節包や靭帯に慢性的なストレスがかかることで、腰部の骨格構造が破綻します。
筋肉と神経の反応
腰の構造は椎弓の亀裂や椎体のずれを防ぐため、脊柱深部にある「多裂筋」や「腸腰筋」といった小さな筋肉は防御的に緊張し、この過緊張によって脊柱はさらに動きを制限し、負荷がさらに椎間関節に集中する悪循環をつくります。
また腹横筋や骨盤底筋など体幹の安定に関わる筋肉の活性が低下すると
腰椎の安定性が弱まり、すべり症や骨への亀裂を誘発する原因になり
椎体が前方にズレてしまうと、神経根が圧迫されることで電気信号の伝達や神経への栄養が阻害され、痛みやしびれ、筋力低下が発生し、血流の低下により組織の回復能力もさらに追いつかなくなってきます。
脊柱と関節の生理学的観点
脊柱は柔軟性と安定性のバランスで動く構造です、
しかし、腰椎分離症やすべり症ではその不安定さから、損傷部位以外での周囲の関節や靭帯、筋肉に代償的なストレスが生じます。
また、骨盤の前傾や胸椎の後弯、頸椎の前弯といった姿勢の変化によって
腰椎にかかる荷重パターンを変え、腰部にかかるストレスを増大させ、亀裂やすべりの重症度をさらに高めます。
脊柱を全体の運動連鎖として捉える
局所異常の全身的影響
腰椎に分離症やすべり症のような局所異常が生じると、まずその椎骨自体の安定性が低下します。
腰椎部では体幹の中心で荷重を支える役割を担うため、部分骨折や前方滑りによって不安定になると、骨盤や胸郭、頸椎といった上下の脊柱構造が代償的に機能します
特に、骨盤の前傾は股関節の屈筋群に持続的な緊張を生み、腸腰筋や大腿直筋の過緊張を引き起こします。骨盤の左右の傾きや回旋のアンバランスは歩行時の重心を偏らせ、膝関節や足部の関節に不安定ストレスを生じさせるなど、下肢の骨格構造に大きあな影響を与えます。
胸椎や胸郭部分では、腰椎の不安定性が上肢に影響し、
胸椎後弯の増加や胸郭運動の制限が起こることで、り、横隔膜や肋間筋の運動パターンにも変化が生じ呼吸時の胸郭拡張が不十分となり、呼吸が浅くなることで副交感神経活動が低下して緊張状態が持続しやすくなります。
頸椎では、腰椎と胸椎の変化にあわせて前弯が過剰になり、首が前に突き出したような姿勢が起こりやすくなります。
これにより頭部重量の支持負荷が増加することで、「頭長筋」「頸長筋」「多裂筋」などの頸部の深部筋が防御的に緊張します。
腰部の深部筋の役割と調整
多裂筋
椎骨間の細かな運動を制御し、椎間関節や椎体への過剰な負荷を抑えます
腰椎の安定性を高めることで、椎間板や椎弓へのストレス集中を軽減する役割も。
腸腰筋
骨盤と腰椎を直接連結し、骨盤前傾や腰椎の過伸展を制御します。
歩行や立位姿勢での荷重移動に関与して、骨盤、下肢の運動連鎖の中で様々な重要な機能を果たします。
横突間筋・回旋筋
椎体間の小さく細かな回旋や側屈の制御を行い、前屈や側屈、回旋などの椎体の動きの整合性を調整・保持をします。
しかし、腰椎分離症やすべり症などの腰椎病変によって、これらの筋群が過緊張すると、脊柱の可動域が制限されるだけでなく、椎間関節への負荷が増えることで、さらなる疼痛や変形を助長する原因ともなります。
筋肉の防御的緊張は腰の不安定性をサポートする一方で、全身の運動連鎖に影響を与え
結果的に全身の動きの効率やストレス分布を変化させ、症状を悪化させることに繋がります。
腰椎分離症・すべり症へのアプローチ
腰椎分離症やすべり症では、これまで説明してきた不安定性を単に固定するのではなく、周囲筋の過緊張や、関節のこまかな動き、血流やリンパの循環を改善することで、脊柱全体の運動連鎖を取り戻します。
椎骨と椎間関節の調整
脊柱のアプローチでは椎骨単体ではなく、上下の椎骨間のこまかな運動を改善します。
腰椎のすべりりや椎弓の亀裂によって、椎間関節が硬化した部分を、適切な位置関係に調整することで、関節包や椎間板にかかる負荷を分散させること、椎骨間の動きが滑らかになり、防御的に緊張していた筋を適切な張りに調整します。
神経・血流・リンパ循環の調整
腰椎分離症やすべり症では、椎体の前方滑りや椎弓の亀裂によって椎間孔が狭くなり神経根が物理的に圧迫されます。
神経根は単に痛みの伝達ではなく、椎間孔が圧迫されることで、神経に酸素などを供給する血流やリンパ循環の調整機能も低下することで、さらに防御的緊張が助長され、筋膜や腱膜を介して血管やリンパ管が圧迫される悪循環が起こります。
毛細血管レベルでの血流が低下してしまうと、細胞への酸素供給が不足し、老廃物や炎症性サイトカインの排出も滞ってきますので、炎症が長期間残りやすく回復に長い期間がかかりやすくなってしまいます。
この循環を改善するためには、筋膜や深部筋の過緊張を緩める、筋肉に圧迫されていた血管やリンパ管が開放し、毛細血管を通る血流とリンパの循環を改善することで、老廃物や炎症性物質の排出を促進することで、悪循環のサイクルを断ち切るのです。
腰椎分離症・すべり症の改善ポイント
腰椎分離症やすべり症は、腰だけの問題ではなく。
椎体のズレや椎弓の亀裂による、深部筋肉の防御的収縮や、血流やリンパの流れの滞りによる。痛みやしびれ、疲労感などを全身的に改善する必要があります。
さくら整骨院では、脊椎や関節、、骨盤などの連鎖、さらに血流やリンパの循環までを一体として整えることで。腰への負担を減らし、痛みの悪循環を断ち切ります。
身体の機能が改善されてくることで、腰の安定感や動きやすさが増してきて、日常動作やスポーツ中の違和感も軽減し、体の中で滞っていた流れがスムーズに動き出すような感覚を実感できるようになるのです。