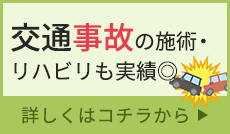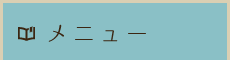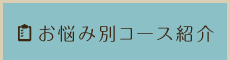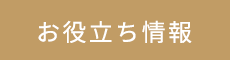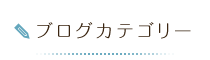「子どもに整体って本当に必要ですか?」
- 子どもの姿勢が気になる
- 集中力がない
- よく風邪をひく
――こうした悩みを持つ親御さんの中には、「整体で改善できるのでは?」と考える方も少なくありません。
ただし、子どもの場合は大人と違う発達過程にあります。
効果的な整体を受けるためには、年齢に応じた正しい知識が必要です。
この記事では、子どもが整体を受ける際の年齢別ガイドと、それぞれの段階での注意点を解説していきます。
出生から始まる「背骨」の発育とは?
赤ちゃんの背骨は、生まれたときから大人と同じ脊柱の彎曲をしているわけではなく
実は、出生から立つまでの発達過程の中で順番に1つずつ生理的彎曲が少しずつ形成されていきます。
新生児期【C字カーブの背骨】
生まれたばかりの赤ちゃんの背骨は、丸くC字状に弯曲しています。
これは、胎内で丸まっていた姿勢の名残で、脊柱の「一次カーブ」と呼ばれるもの。
この時期はまだ首や腰の筋肉が発達しておらず、背骨全体で体を支えている状態です。
首すわり → 頸椎の前弯ができる時期
生後3〜4ヶ月ごろになると、うつ伏せで顔を上げる動作が増えてきます。
この「首を持ち上げる」動きによって首の前弯(頸椎カーブ)が形成されていきます。
つまり、首を支える筋肉と神経の発達が、姿勢形成の重要なファーストステップとなるのです。
ハイハイ → 腰椎の前弯ができる時期
次の大切な段階が「ハイハイ」です。
四つ這いで動くことで、背中から腰・骨盤にかけての筋肉が発達し、腰の前弯(腰椎カーブ)が形成されていきます。この段階をしっかり通過することが、のちの姿勢の安定・体幹の発達・自律神経の成熟にも大きく関わります。
ハイハイを十分にせずに早く立って歩き出すと、体幹が未発達のまま重力を支えることになるため、成長後に「猫背」「反り腰」「集中力の低下」などに影響が出るケースもあります。
ハイハイは全身の神経を育てる
赤ちゃんのハイハイは、ただの移動運動ではありません。
実は、脳と体をつなぐ神経ネットワークを発達させ、原始反射と呼ばれる
身体のバランスと機能を統合していく重要な発達ステップなのです。
原始反射ってなに?
赤ちゃんは生まれたとき、無意識に働く「反射運動」をいくつも持っています。
これを原始反射といい、生命を守るための本能的な動きです。
代表的なものとして
- モロー反射(びっくり反射)
- 把握反射(手を握る)
- 非対称性緊張性頸反射(ATNR)
- 対称性緊張性頸反射(STNR)
など。
日常でイメージしやすいのが、赤ちゃんをベットに寝させようとした時に、背中がベットにあたって目が覚めてまた泣き出してしまう。というのが「モロー反射」の典型例です。
これらの反射は、成長とともに識的でスムーズな随意運動を行うために「統合」され、消失することで、赤ちゃんは意図的でスムーズな随意運動を行えるようになります。
もし原始反射が十分に統合されないまま次の発達段階に進むと
「ハイハイや寝返りの動作がスムーズにできない」
「座る・立つ・歩くといった基本動作にぎこちなさが残る」
「注意力や集中力が散漫になりやすい」
「姿勢が不安定になり、猫背や反り腰などが起こりやすい}
といった影響が現れることがあります。
ハイハイ期は「原始反射の統合期間」
ですから、ハイハイの動きは、まさにこの「統合」を促す大切な時期で
特に関係が深いのが
ATNR(非対称性緊張性頸反射)
→ 首を向けた側の腕・脚が伸び、反対側が曲がる反射。
→ ハイハイではこの反射が徐々に統合され、左右の連動の対角運動ができるようになります。
STNR(対称性緊張性頸反射)
→ 頭を上げると腕が伸びて脚が曲がり、頭を下げると逆になる反射。
→ ハイハイ中の「頭を上げて進む」「顔を下げて休む」動きで自然に統合されます。
この2つの反射が統合されることで
「首や背骨の安定」
「バランス感覚の発達」
「姿勢保持能力の向上」
が進みます。
ハイハイは「脳と体をつなぐ訓練」:非対称性緊張性頸反射
ハイハイのとき、赤ちゃんは「右手と左足」「左手と右足」を交互に動かします。
この対角運動は、左右の脳(右脳と左脳)をつなぐ「脳梁」という神経束の発達を促します。
つまりハイハイは
右脳:空間感覚や感情
左脳:言語・論理をバランスよく連携させる練習。
この連携がスムーズに育つことで、姿勢制御・バランス感覚・集中力・感情の安定など
発達の基盤となる要素が整い、四つ這い姿勢で背骨を支えることで、脊髄神経の伝達路が整い、自律神経の働きも安定します。
ハイハイで育つ体幹と全身感覚
ハイハイは全身を同時に使い、床を押す・支える動作を繰り返します。
このとき働くのが「固有感覚」と呼ばれる感覚で、
この感覚器が刺激されて、身体の位置や力の入れ具合を脳に伝えることができるので
ハイハイを通じて身体の固有感覚の発達が刺激されるのです。
さらに、ハイハイは重力に抗して体のバランスをとる動きでもあります。
その結果、平衡感覚や小脳、脳幹〜大脳皮質をつなぐ神経回路が同時に活性化し、
「動き」と「感覚」を結びつける運動連合野が発達しまので
ハイハイは「全身のセンサーと神経回路をまとめて調整する調整期間」でもあり
姿勢保持が上手になる
転びにくくなる。ぶつけにくくなる。という力加減や
バランス感覚が良くなる
といったメリットがすべて連動して育つのがハイハイの時期なのです。
ハイハイの期間が短いとどうなる?
原始反射と運動発達の関係
通常、この原始反射は発達の過程で「統合」され、意識的な運動や姿勢制御へと切り替わりますが
ハイハイの期間を十分に経ずに歩行へ移行してしまうと、
原始反射が未統合のまま残りやすく、その後の姿勢や自律神経の働きに影響が出ることがあります。
「寝返りの動作がスムーズにできない」
「座る・立つ・歩くといった基本動作にぎこちなさが残る」
「注意力や集中力が散漫になりやすい」
「姿勢が不安定になり、猫背や反り腰などの姿勢不慮が起こりやすい」
といった影響がでることがあります。
背骨と骨盤のバランスが完成に向かう「幼児期」
幼児期に入ると、立つ・走る・跳ぶなどの動作が増え
重力の中で身体を支える「抗重力筋」が特に発達します。
このとき重要なのが、背骨の「S字カーブ」と骨盤の安定。
背骨のしなやかなカーブは、衝撃を吸収しながら頭部や内臓を支えますので
骨盤が前に倒れすぎてしまうと → 反り腰・腰痛・集中しづらい姿勢
骨盤が後ろに倒れすぎてしまうと → 猫背・呼吸が浅い・疲れやすい
という原因につながりやすく
骨盤の角度と背骨のカーブのバランスが、姿勢の土台となるのです。
遊びで育つ「姿勢筋」
子どもにとって「遊び」とは最高の発達刺激です。
走る・登る・ぶら下がる・転がるといった動きが、体幹や背骨を支える筋肉を自然に育てつのです。
特におすすめなのが
トンネルくぐりのような「四つ這いでの遊び」
一本橋のような「バランス遊び」
ぶら下がり・逆上がりなどの懸垂系の運動で
これらの動きは、筋肉だけでなくバランス感覚や、固有感覚といった身体の位置感覚や「視覚」を統合し、脳と身体の連携を高めていきます。
小学校は座る姿勢が激増
小学校に入ると、学校の授業で座って勉強する時間が一気に増えますが
姿勢が安定していないまま長時間座ると、背骨や骨盤への負担が大きく自律神経に影響をあたえやすくなります。
メカニズムとしては
猫背 → 胸郭が狭まり、呼吸が浅くなる → 酸素不足 → 集中力低下
頭が前に出る → 首・肩の筋緊張 → 交感神経優位 → 落ち着きにくい
つまり、「座り姿勢が悪い子」は、単にだらけているのではなく、
体幹・神経発達のバランスが未熟なサインである場合も。
成長期の「姿勢ぐせ」は骨格を決める
小学生〜中学生にかけては、背骨や骨盤の成長スピードが速く、
この時期の姿勢ぐせが、そのまま大人の姿勢を形づくりやすい時期
と言っても過言ではありません。
また、背骨の中を通る脊髄には、脊柱管という自律神経の大切な経路があり
姿勢が整うことで、この神経の伝達がスムーズになりますので、
この時期における、自然な生理的彎曲を整えておくことで
「落ち着きやすくなる」「睡眠リズムが安定する」「集中力が高まる」といった、心身の調子を整えることになってくるのです。
中高生は「ストレス」と「自律神経の乱れ」に注意
中学生〜高校生は、心身ともに大きく変化する「第二の成長期」
身長が急激に伸び、骨格が完成に向かう一方で
ホルモンバランスや自律神経の働きが不安定になりやすい時期。
この時期に姿勢や身体バランスが乱れると、
単なる「姿勢の悪さ」だけでなく、頭痛・肩こり・倦怠感・集中力の低下・情緒不安定、場合によっては起立性調節障害などの症状につながることもあります。
詳しい解説はコチラ
▼▼▼
成長曲線と姿勢のゆがみ
思春期には骨の成長が筋肉よりも早く、筋肉のアンバランスが生じやすくなります。
猫背のように背中が丸くなったり、腰の片側が張るような骨盤の歪みが強くでたり。ストレートネックと呼ばれる首が前にでるような状態に陥ったりすることで、自律神経のバランスに影響し起立性調節障害のような「立ち上がったときのめまいやだるさ」を引き起こすことがあります。
学生のあらゆる生活ストレスが自律神経に影響
中高生はテストや部活、人間関係など心理的ストレスがどうしても増加しやすい時期で
現代病ともいわれるスマホ・タブレットは
長時間、首や肩に負荷をかけることで、胸郭を圧迫し呼吸が浅くなることで自律神経が乱れやすく、結果として「起立性調節障害」や「集中力低下」といった症状を引き起こします。
部活動による身体の偏り
また意外にも、実はスポーツをやっているから「健康」というわけでなく
片側ばかり使う運動や過剰な練習は体のゆがみを助長する場合や
無理をおしてプレーをすることによる代償運動の積み重ねが
「利き腕偏重」や「重心の偏り」、「脊柱の回旋偏位」「過度の柔軟性による骨盤不安定性」などを生じさせ、不調の原因となることがあります。
「悪い姿勢」に気づかない
実は、子どもの多くは自分の姿勢の悪さを「悪い」と自覚していません。
特に小学生くらいまでの年代は、大人から見るとあきらかに姿勢が悪い。と分かる状態でも、本人は「これが楽」「これが普通」と感じています。
ですから、非常に重要なことは
「悪い」と自覚していない以上、「姿勢を正す意味がない」という判断となり
結果的に「親がうるさいから」あるいは「親にうるさく言われない」為に
姿勢をただそうとするお子さんはいますが
姿勢を正さなければ「将来すごく損をする」と思って自主的に姿勢を正すお子さんはまずいません。
「損に気づける身体感覚」を育てることが大切
ですから、現在の姿勢不慮がどれだけ損をしているのか?
ということをお子さんに知ってもらうためには
単に「口で言って聞かせても」お子さんはその重要性を理解できません。
ですから、お子さんが自身が
整体を受けて
「あの整体をうけるとなんかいいな。」
「整体を受けるとなんか姿勢がいい気がするな」
ということを実感されることこそが、重要です。
当然、おこさんに上手に整体をうけてもらえるように先生が上手に関わり
施術や整体というものが、よく理解できないお子さんに、本質的で直感的に良くなったような気がするという施術者の技術を、先生が持ち合わせている前提です。
子ども整体は「体の発達に合わせて」
子どもの身体は単に骨や筋肉だけでできているわけではなく、
脊柱・骨盤の骨格構造とそのバランス
原始反射をはじめとあうる神経系の発達
自律神経や感覚器官といった神経の統合
がバランスよく育つことで、健康で安定した発育につながります。
そのため、整体を受けるタイミングは年齢で決めるのではなく、
子どもの発達段階を見極めて、お子さんの状態や気分に合わせて柔軟に考えるのが理想。
子供があまり改善する気持ちがない時に
「無理に短期間で身体を改善しようとしても、結局はすぐに自分で元に戻ってしまいます」から
最初は、「全身のチェックと悪いところの評価」くらいからスタートし
施術を受ける良さを子供が「自ら実感できる」あるいは「自ら受けたい」と感じて
相談してくる。くらいのタイミングがもっとも改善しやすく、結果的に長期的な根本改善につながります。
整体デビューポイント!
子ども整体は、発達段階や体の状態に応じて、いつでも大丈夫!
重要なのは、年齢にとらわれず、その子の体と神経の発達に合わせたアプローチをすることです。
ですから、まずは発育発達に精通し、お子さんを無理に整体することなく
自然に整体の良さを伝えてくれる先生。を探すのが1つのポイント。
また早すぎる矯正は必要なく、まずは自然な動きや遊びを通じた神経・構造・感覚の統合が最も重要で、整体は受けることが「一番の目的」というより
子どもが自分の体の状態に気づき、将来の健康的で自然な身体を学ぶスタートです。