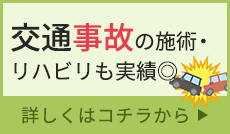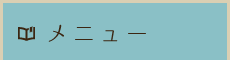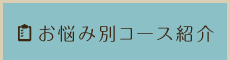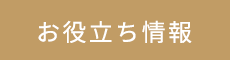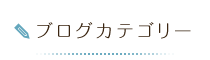岡山のスポーツ障害治療 | 岡山駅徒歩5分のさくら整骨院
「練習後に痛みが出る」「フォームを変えても症状が改善しない」
そんなスポーツ障害にお悩みではありませんか?
スポーツ障害の主な原因
スポーツ障害は、筋肉や関節の疲労だけでなく
「脊柱や骨格・骨盤の歪み」
「成長による柔軟性の低下」
「自律神経伝達の乱れ」など
全身の連動性の崩れが深く関係しています。
スポーツ障害へのアプローチ方法
「脊柱・骨盤の歪み」「筋連鎖」「神経の働き」を整えることで、
再発を防ぎながら、しなやかで力の出しやすい身体を構築し
パフォーマンスを支える身体づくりをサポートします。

「練習を休んでも、痛みが改善しない」
「正しいフォームが分からないまま、いつまでも症状が改善しない」
こういうことは、スポーツ現場でよく耳にする悩みです。
それは、単なるケガでなく積み重ねによる骨格機能の異常です。
その原因は
筋肉のアンバランス
関節の動きの偏り
背骨から始まる運動連鎖の乱れが
などが背景として潜んでいて
特に現代のスポーツは、高い技術と反復練習が求められ
結果的に身体のどこか一部に負担が集中し慢性的な炎症や痛みを生じるケースが増えています。
この記事では
▶スポーツ障害の基礎知識
▶部位別の代表的な障害とメカニズム
▶筋肉・関節・脊柱・神経の関係
などを通して、スポーツ障害の「仕組み」をわかりやすく解説していきます。
スポーツ障害って?
スポーツ障害は大きく分けて
「急性外傷」 と 「慢性障害:オーバーユース」 の2つに分類され
その生理学的な発生機序を理解することが
適切な対応が可能となり、早期に症状を改善することに繋がります。
急性外傷
突発的な「衝撃」や「転倒」で起こるケガで、スポーツ活動の中で
瞬間的に強い力が加わり、筋肉・靭帯・骨が損傷することで
「スポーツ外傷」と言われことも。
具体的には
「試合中のタックルやコンタクトプレー、ジャンプの着地失敗、急な方向転換」などで
捻挫や、靭帯損傷、筋挫傷・肉離れ脱臼、骨折などがこ
この「スポーツ外傷」にあたります。
急性外傷の生理学的メカニズム
特徴として
受傷直後に「ズキッ」や「ズキズキ」といった
鋭い痛みが出ることがほとんどで
痛めた部位の「腫れ、内出血、熱感」などの炎症症状や
筋肉・関節の「可動制限や筋の防御反射」が発生し
症状が重たい場合「虚脱、灼熱感、激痛」いった症状をかんじることもあります。
生理学的メカニズム
外力によって筋線維・靭帯・血管が損傷すると
「損傷細胞から炎症性物質のサイトカイン」が放出されることで
血管拡張の拡張 → 局所の血流増加 → 腫れ・熱感
血漿成分の漏出 → 組織の浮腫
痛覚受容器の感作 → 鋭い痛み
が起こります。
【筋防御反射って?】
この筋の防御反射は脊髄反射を介して損傷部を動かさないようにす働きで
「筋防御反射」と呼ばれます。
この防御反射によって、周辺の関連筋の過緊張や可動域制限を起こすことで
痛めた場所の損傷の拡大を防ぐ一方、
動きの制限・二次的な血流悪化を引き起こします。
そして、損傷後「数日〜1週間」程度で
「線維芽細胞」
と呼ばれる細胞が働くことで
「瘢痕組織」
と呼ばれる回復に必要な組織形成し回復するための下地を作ります。
しかし、注意ポイントとして、この瘢痕化の過程で損傷部位周辺を大事に安静にしすぎると
瘢痕化された組織が硬くなり、可動域制限が残ったまま治癒するこで違う場所を痛める原因になることが多々あります。
ですから、早期からリハビリを開始させられるのは、この瘢痕化を防ぎ
早期復帰の妨げにならないようにするためです。
まら外傷の場合、初期対応が回復期間に大きく影響します。
救急の現場などでも耳にすることもありますが
基本的には
RICE処置=「安静・冷却・圧迫・挙上」が早期回復には重要です。
オーバーユースの生理学的メカニズム
オーバーユースの特徴として
- 初期は軽い違和感や鈍い痛みから
- 運動初期あるいは運動中に痛みが出現し、休息で一時的に改善する
- 繰り返し起こることで、持続痛や可動域制限も併発
- 最終的には筋力低下や痛みによる可動域制限で、競技の離脱を招いてしまいます。
生理学的メカニズム
【微小損傷の累積】
通常は休息と血流によって修復されるのですが
投球や、ランニングなど
「同じ動作の繰り返し」で
筋線維や腱、骨膜、靭帯などに微細な損傷が蓄積し
修復するよりも、損傷の蓄積が上回る状態が続くことで
慢性的な炎症へと移行します。
損傷部では炎症性サイトカインが持続的に分泌され
血流停滞や局所の低酸素状態が起こり、組織の線維化や瘢痕化が進行することで
組織の弾力性が低下し、さらなる損傷の蓄積を助長します。
【神経・筋の適応変化】
慢性的な炎症刺激は、末梢および中枢神経系に「感作」という症状を引き起こします。
末梢性感作では
侵害受容器の閾値が低下し、動かすだけで痛みを感じやすくなる。
中枢性感作では
脊髄で痛み信号が増幅され、実際の損傷以上の痛みを感じるようになる。
この過程で「筋防御反射が持続」し、周囲筋の過緊張や関節のアンバランスが生じることで
さらに症状を悪化させる原因を増幅させます。
【血流と代謝の悪循環】
慢性的な筋緊張や炎症により、局所の血管収縮が続くことで筋や腱への酸素と栄養供給が低下します。
その結果、乳酸や代謝産物が蓄積し、pHが低下することで痛覚受容器が刺激されます。
さらに線維芽細胞が過剰に活性化し、瘢痕化が進行することで
疲労骨折・腱炎などへとつながる原因となります。
原因とメカニズム
| 分類 | 主な原因 | 生理学的背景 |
|---|---|---|
| 急性外傷 | 外力・衝突・転倒 | 組織が外力に耐えられず損傷 |
| 慢性障害 | 過剰使用・フォーム不良 | 損傷の蓄積・血流低下・瘢痕形成 |
| 機能的要因 | 柔軟性不足・筋力差・関節制限 | 特定部位への負担集中 |
よく発生する部位別障害
| 部位 | 主なスポーツ障害 |
|---|---|
| 肩 | 野球肩、腱板炎、インピンジメント症候群 |
| 肘 | 野球肘、テニス肘、ゴルフ肘 |
| 腰 | 腰椎分離症、腰椎すべり症、腰椎椎間板ヘルニア |
| 膝 | ジャンパー膝、オスグッド病、半月板損傷、膝蓋腱炎 |
| 足 | シンスプリント、足底筋膜炎、アキレス腱炎、捻挫 |
肩の代表的スポーツ障害
肩関節周辺のスポーツ障害
- 野球肩:投球障害肩
- 腱板炎
- 肩峰下インピンジメント症候群
- SLAP損傷:上方関節唇損傷
- 肩関節脱臼・亜脱臼
- 上腕二頭筋長頭腱炎
などがあげられ
主症状として
- 投球や腕の挙上での痛み【特に外転60〜120°】
- 夜間痛や就寝中のうずき
- 肩の「引っかかり感」や「可動域制限」
- 時には「力が入りにくい」「速いボールが投げれない」
といった症状まで
慢性期にいたっては筋萎縮が起こります。
特に棘上筋での筋萎縮が顕著で肩甲骨の動揺性も増加しするのも特徴の1つ。
原因と生理学的メカニズム
【投球やスイング動作の繰り返し】
オーバーヘッド動作では、肩関節が外旋・外転位で強く牽引されます。
このとき、棘上筋・棘下筋・小筋・肩甲下筋と呼ばれる
インナーマッスルに強い張力がかかることで
「腱線維の微細な断裂」や「滑液包の炎症」などが発生します。
また、投球のフォロースルー期では肩前方への牽引力が働き
上腕骨頭の前方偏位や関節包の伸張が生じやすく
長期的には「関節唇損傷」「反復性亜脱臼」などを引き起こします。
【肩甲骨の可動制限・安定性低下】
肩甲骨は、上肢帯の土台となる部分ですが
前鋸筋・僧帽筋下部・小菱形筋といった肩甲骨周囲の機能が低下するこにより
肩甲骨の上方回旋・後傾・外転運動が十分に起こらないとで
上腕骨頭が肩峰下で衝突を起こすことでインピンジメン症候群を引き起こし
腱板の「摩耗・炎症・石灰沈着」を誘発します。
【姿勢・脊柱アライメントの影響】
猫背・巻き肩姿勢では、胸椎の後弯・肩甲骨の外転・前傾が強くなり
この状態では、特に肩関節の外旋・挙上の可動域制限され、動作のたびに腱板や滑液包が擦れることで慢性的炎症を起こします。
また、「胸椎・頸椎」の可動性低下により
肩甲帯の神経支配である副神経・肩甲背神経が乱れ、筋の協調性が失われます
【肩周辺の筋力・柔軟性のアンバランス】
大胸筋・広背筋といった大きな筋肉が過緊張すると
その対となる棘上筋・菱形筋・僧帽筋下部などの安定筋が抑制されます。
すると
肩関節における肩甲上腕リズムが破綻することで
肩甲骨が不安定になり、腱板や関節包への負担が増大します。
このアンバランスは、神経反射(相反抑制)や筋膜連鎖にも影響し
単なる筋肉の疲労ではなく運動制御系の機能低下として現れます
痛みの原因が「筋肉」ではなく、「骨格・関節包・神経制御系のアンバランス」で
→ 肩のスポーツ障害は
脊柱「特に胸椎」・肩甲骨・上腕骨の運動連鎖の破綻
によって生じることが大きな原因となります。
のスポーツ障害
肘の代表的スポーツ障害
肘関節周辺のスポーツ障害
- 野球肘(内側・外側上顆離断性骨軟骨障害)
- テニス肘(上腕骨外側上顆炎)
- ゴルフ肘(上腕骨内側上顆炎)
- 肘関節離断性骨軟骨炎(OCD)
- 上腕二頭筋腱遠位部断裂
- 尺骨神経障害
などの病変が代表的。
主症状として
- 投球・打撃・スイング時の肘の内・外側の痛み
- ボールを投げる・握る・スナップを効かせる動作で痛み
- 関節の可動域制限や「ひっかかり感」
- 進行すると肘の変形や可動制限、パフォーマンスの低下
- 神経障害を伴う場合、手のしびれ・握力低下がみられることもあります
慢性期では「腱の肥厚化・滑走障害」が生じ、肘関節の安定性が損なわれるケースも。
原因と生理学的メカニズム
クラブやラケットでのスイングでは、「肘関節に強い剪断力と回旋力」が加わります。
投球時では、上腕骨内側上顆に牽引ストレス、外側には圧縮ストレスが集中し
これがさらに長期的なストレスがかかると、腱・靭帯の微細損傷が起こり
骨軟骨の分離する離断性骨軟骨炎を発祥するケースも。
特に成長期では骨端線(骨の成長軟骨)がの部分が弱いため
成人よりも損傷リスクが高いのが特徴。
肘のスポーツ障害の特徴
 野球・テニス・ゴルフ・体操など上肢を繰り返し使う競技に多発
野球・テニス・ゴルフ・体操など上肢を繰り返し使う競技に多発
痛みの原因は筋肉ではなく、骨格・腱・靭帯・神経制御系のアンバランスにあります
→ 肘のスポーツ障害は単なるオーバーユースでなく
肩・肩甲骨・体幹の運動連鎖の破綻によって生じる障害です。
【肩・肩甲骨の可動性低下による肘への負担増加】
肩甲骨や肩関節の可動制限により、スイング動作で必要な外旋角度が不足すると
その分の力を肘で補うことになります。
結果として内反トルクが過剰になり、内側上顆炎や靭帯損傷を誘発します。
また、肩甲骨の上方回旋や後傾が不足している場合
肘の動作連動がうまくいかずに筋腱の牽引ストレスが局所に集中しやすくなり、肘の障害を発生させやすくなります。
【前腕の筋力・柔軟性のアンバランス】
前腕屈筋群・伸筋群のバランスが崩れると、肘関節全体の安定性が低下し
スイングや打撃時の肘周辺の安定性が著しく低下します。
結果的に前腕屈筋群が過緊張すると内側上顆炎を、伸筋群の場合だと外側上顆炎を起こしやすくなります。
この状態は、「固有受容感覚」と呼ばれる神経筋制御が腱の滑走障害により悪くなり
筋疲労ではなく、神経反射・相反抑制の乱れによって運動制御系の機能が著しく低下することで
症状もさらに慢性化しやすくなります。
【姿勢・体幹アライメントの影響】
体幹や骨盤の回旋制限、胸椎の可動性低下があると
投球動作の回転エネルギーが上肢に伝わりにくくなり、結果として肘が「代償」して過剰に使われます。
特に「猫背・巻き肩姿勢」では、肩関節の外旋が制限され肘の牽引ストレスが増大。
さらに頸椎、胸椎の動きが硬いと、腕神経叢〜尺骨神経の滑走性が悪化し、
肘周囲の痛みやしびれをより増幅させます。
腰部・仙腸関節の代表的スポーツ障害
腰・仙腸関節のスポーツ障害
- 腰椎分離症・分離すべり症
- 筋・筋膜性腰痛
- 仙腸関節障害
- 腰椎椎間板症
- 梨状筋症候群
主症状
- 腰の鈍い痛みや張り感
- 体幹の回旋・後屈での痛み
- 前屈・ジャンプ動作での疼痛
- 臀部から下肢への放散痛(坐骨神経症状)
- 起床時や練習後のこわばり・重だるさ
慢性期では腰部伸展制限や骨盤の非対称性が目立ち、体幹のコアスタビリティが低下します。
原因と生理学的メカニズム
【繰り返す伸展・回旋ストレス】
バレーボール・バスケットボール・サッカーなどでは
キックや、ジャンプ着地時に腰椎へ反復的な伸展・回旋ストレスが加わります。
この繰り返しにより、椎弓部に微小骨折が生じ「腰椎分離症」を発症。
さらに、椎間板や椎間関節にもせん断力が加わり、
線維輪の微細損傷 → 髄核内圧上昇 → 神経根刺激へと進行していきます。
腰部疾患の急性では鋭い腰痛、慢性化では鈍い張りや可動制限が残ることも。
【仙腸関節の可動性異常】
仙腸関節は体幹と下肢の力を伝達する「衝撃吸収のハブ」。
「片脚荷重や蹴り動作」「骨盤のねじれ」が繰り返されると、
仙腸関節の滑動性が失われ、仙骨の前傾固定・後傾固定が起こります。
この微細なズレは多裂筋・骨盤底筋・大殿筋・腸腰筋などの
骨盤帯の筋群の筋緊張バランスを崩し、腰椎の回旋軸を狂わせます。
結果として
「腰椎・仙骨・腸骨」の運動連鎖が乱れ、慢性腰痛・臀部痛・下肢の違和感などを生じさせます。
【腰背部筋膜・神経支配】
腰背部は胸腰筋膜と呼ばれる筋膜によって
広背筋・大殿筋・ハムストリングスが連動しており
この筋膜連鎖が硬くなると、筋膜間の滑走不全が生じ
体幹の屈曲・回旋動作時に痛みや違和感が出現します。
また、仙腸関節や腰椎周囲には
上殿神経・腰神経叢などの小さな神経の枝が密集しており、
軽度な炎症でも感作という神経過敏が生じやすく、慢性痛に移行しやすい特徴があります。
【姿勢・脊柱アライメントの影響】
胸椎や骨盤の動きが硬いと、腰椎が代償的に過剰運動を起こします。
特に「胸椎伸展制限」や「骨盤後傾姿勢」は、腰椎の伸展ストレスを増大させ、
分離症や椎間関節症を悪化させます。
また、骨盤の捻転や下肢長差があると
片側の仙腸関節に偏った荷重がかかり
慢性の炎症や筋膜性疼痛を引き起こしやすくなります。
【体幹機能の低下】
腹横筋・多裂筋・骨盤底筋・横隔膜による
「腹圧システム」が十分に働かないと
腰椎の支持性が低下し、わずかな動作でも関節や筋に負担がかかりやすくなってしまいます。
この体幹安定性の低下は
筋出力制御のタイミングにも影響し
「痛みの再発」「フォームの崩れ」につながります。
膝の代表的スポーツ障害
膝周辺のスポーツ障害
- ジャンパー膝(膝蓋腱炎)
- 腸脛靭帯炎(ランナー膝)
- 半月板損傷
- 前十字靭帯損傷
- 内側側副靭帯損傷
- 膝蓋骨脱臼・亜脱臼
などが代表的症状。
主症状
- ジャンプや着地、ダッシュ動作での膝前面の痛み
- 走行・方向転換時に膝の内側・外側に痛み
- 階段の昇降やしゃがみ動作での痛みや違和感
- クリック音・引っかかり感・不安定感
- 腫れや可動域制限、筋萎縮(特に大腿四頭筋)
慢性期では腱・靭帯の肥厚化や関節包の拘縮が進み、膝関節の衝撃吸収機能が大きく低下します。
原因と生理学的メカニズム
過度なジャンプ・着地・方向転換動作の繰り返し
バスケットボール・バレーボール・サッカーなどでは、
着地や切り返しの際に膝関節に強い伸展力と回旋ストレスが加わります。
このとき、膝蓋腱や腸脛靭帯に過剰な張力がかかり、
微細損傷や腱付着部の膝蓋腱炎や腸脛靭帯炎を起こします。
また、膝関節屈曲位での急激な外旋は、半月板損傷や靭帯損傷を誘発。
特にACLは「脛骨の前方すべり+回旋力」で断裂しやすく、
一度の損傷が長期的な関節不安定を引き起こし、手術を行なった場合でも
復帰までの期間を長期間要するケースが多く、再発が多いのも特徴です。
【股関節・骨盤の可動性の低下】
股関節や骨盤の回旋制限があると、地面からの衝撃を十分に吸収できず
膝でその代償を負担します。
特に股関節外旋筋群や殿筋群の機能低下は、膝の内反や脛骨外旋を誘発し
膝蓋腱や半月板へのストレスを増大させます。
また、骨盤の前傾過多では大腿四頭筋が過緊張し
逆に後傾姿勢ではハムストリングスが過緊張となり
膝関節全体としての動的安定性が損なわれ、膝周辺の障害を発生させやすくなります。
【筋力・柔軟性のアンバランス】
大腿四頭筋とハムストリングスの筋力バランスが崩れると、
膝蓋骨の追従性が乱れ、膝蓋骨外方偏位や摩擦が生じます。
また、ハムストリングスや下腿三頭筋の柔軟性低下は、
膝関節の衝撃吸収を阻害し、関節軟骨へのストレスを増加させます。
このアンバランスは筋肉の問題だけでなく
相反抑制と呼ばれる神経の反射や固有感覚の乱れにより、運動制御そのものに影響します。
【姿勢・脊柱アライメントの影響】
胸椎や骨盤の動きが硬く、体幹の前後バランスが崩れると
膝関節での荷重線が乱れます。
猫背・骨盤後傾姿勢では、膝関節が屈曲位で荷重され続け
膝蓋大腿関節への圧迫ストレスが増加します。
また、足部の回内・扁平足は脛骨の内旋を伴って膝の内反を助長し、
鵞足炎や腸脛靭帯炎の原因になります。
体幹・骨盤・下肢のアライメントが連動して働かないと
膝だけに過剰なトルクが集中し、慢性化・再発を繰り返します。
足部・足関節の代表的スポーツ障害
足部・足関節のスポーツ障害
- 足関節捻挫(前距腓靱帯損傷・三角靱帯損傷)
- アキレス腱炎・アキレス腱周囲炎
- 足底腱膜炎
- シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)
- 有痛性外脛骨
- 中足骨疲労骨折
- 後脛骨筋腱炎・腓骨筋腱炎
などが代表的。
主症状
- ジャンプや着地、ダッシュ時の足首の痛み・違和感
- 立ち上がりや歩行開始時の踵部痛
- ランニング中の足底・すねの鈍痛
- 足関節の不安定性や「グラつき」
- 慢性期では腱や靱帯の肥厚・癒着により、足関節の安定性とバランス能力が低下します。
足部・足関節のスポーツ障害の特徴
ランニング・ジャンプ・方向転換を伴う競技に多発し
痛みの原因の多くは「アーチ機構」や「神経制御系の乱れ」によるものが多く
骨盤・股関節・下腿・足部アーチを含む運動連鎖の崩れによって生じます。
原因と生理学的メカニズム
着地・方向転換による急激な回旋ストレス
ジャンプ着地や切り返しの際、足関節には強い内反・外反ストレスがかかります。
特に内反捻挫では前距腓靱帯・踵腓靱帯が強く牽引され靭帯の断裂を引き起こしやすくなります
捻挫した時の損傷部では炎症性サイトカインが放出され、
「血管拡張」「浮腫」「疼痛受容器の感作」を引き起こします。
さらに、関節包内の固有感覚受容器の機能低下により、
「足首が不安定」「踏ん張れない」といった運動制御障害が残ります。
【アキレス腱・足底腱膜への過負荷】
腓腹筋・ヒラメ筋の過緊張や、足部の過回内により、
アキレス腱や足底腱膜が絶えず牽引されます。
この状態が続くと、腱線維の微細断裂と慢性炎症が起こり
腱の肥厚・滑走不全・線維化へと進行します。
特に足底腱膜炎では、踵骨内側突起での腱膜牽引が持続し
朝の一歩目での強い疼痛や慢性的な違和感が特徴となります。
【足関節の骨格構造の影響】
足のオーバープロネーションと呼ばれる「過回内」では、
内側縦アーチが低下させ
距骨下関節の回旋異常や脛骨内旋を誘発。
その結果、膝内側や足底内側へのストレスを増大させます。
一方、過回外(オーバースピネーション)では
衝撃吸収能力を低下させ
腓骨筋群や外側靱帯群への負担が蓄積しやすく
楔状骨や、立方骨、舟状骨といった足部の小さな関節に影響を与え
足部障害の慢性化や再発の原因となる温床にもなります。
【筋力・柔軟性のアンバランス】
下腿三頭筋や後脛骨筋の過緊張は、足関節の底屈優位を生み
背屈制限をもたらします。
その結果、着地動作での衝撃吸収が不十分となり、
足底腱膜やアキレス腱に過負荷が集中します。
また、足趾屈筋群・腓骨筋群・前脛骨筋などの筋力低下は、
足部アーチの支持力を低下させ、疲労骨折や足底腱膜炎を助長します。
このアンバランスは、単なる筋力差だけでなく
固有感覚の乱れや相反抑制の不全により、
運動制御レベルでのエラーとしてある日、突然、症状として表面に顕在化されるのです。
【姿勢・脊柱アライメントの影響】
骨盤の前傾過多や脊柱の後弯増大により、
重心が前方偏位すると、足部への荷重が増加します。
また、体幹の回旋制限や股関節外旋筋の弱化は、
足関節へのトルク負荷を増大させます。
骨盤・脊柱といった上位構造の歪みは、足部アーチの崩壊を誘発し
捻挫やアキレス腱炎の再発要因にもなります。
回復と改善のポイント
👉炎症を鎮めるだけでなく、血流と組織代謝の再活性化が重要。
👉関節可動域を維持しながら、フォーム修正と荷重バランスの再構築を行う。
瘢痕化や癒着をリリースし、神経―筋―筋膜の連動性を取り戻すことが最も重要で
脊柱から全身を見直すことで、
単なる「局所治療」では届かない、根本的な機能回復と再発予防が実現します。
スポーツ障害の根本改善まとめ
スポーツ障害は「単なるケガ」ではなく
脊柱・骨盤・筋肉・神経の連動性の乱れによって生じる「全身的な機能障害」です。
急性外傷のような一瞬の衝撃による損傷から
オーバーユースのように繰り返しの負担で起こる慢性障害まで
背景には
「使い方の偏り」「姿勢・柔軟性の低下」「血流や神経伝達の乱れ」が共通して存在します。
特に、肩・肘・腰・膝といった主要なスポーツ障害では
痛みの出ている部位だけでなく
その運動連鎖の起点となる胸椎・骨盤・体幹の動きを整えることが重要です。
-
肩の障害では「胸椎や肩甲骨の可動性低下」
-
肘の障害では「肩甲帯・体幹の回旋制限」
-
腰の障害では「骨盤のねじれ・仙腸関節の可動不全」
-
膝や足の障害では「股関節・骨盤・足部アーチの連動性」
これらを的確に見極め
脊柱を中心とした全身バランスを回復させることで再発を防ぎ
しなやかで力の出しやすい身体づくりが可能になります。
つまり、スポーツ障害の根本改善とは「痛みを取ること」ではなく、
身体全体の機能を再構築し、正しい運動連鎖を取り戻すことが最重要なのです。