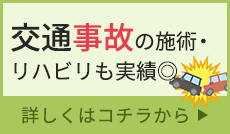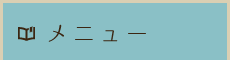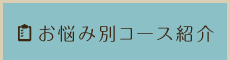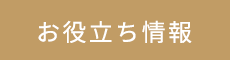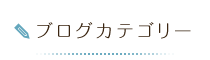岡山の起立性調整障害治療 | 岡山駅徒歩5分のさくら整骨院
朝起きられない、立ちくらみ、倦怠感が続く息苦しさがある、集中力が落ちる
学校に行くのがつらい…
それは「起立性調整障害」が原因かもしれません。
生理学的な構造・機能に基づく手技を行うさくら整骨院では、脊柱・骨盤・下肢・筋肉・胸郭・神経・血流の滞りを整え、起立性調整障害の症状を根本から改善します。
体幹や下肢、脊柱の連動を回復させ、神経や血流が本来の働きを取り戻す環境をつくることで、朝のだるさや立ちくらみを和らげるだけでなく、再発しにくい身体作りを実現します。
岡山で起立性調整障害のつらい症状を根本から改善したい方へ
朝不調がない、快適で自然な日常を取り戻しましょう。
朝、目は覚めているのに、どうしても体が動かない。
学校に行かなきゃと思っても、立ち上がるだけで気分が悪くなったり、頭がボーッとしたりする。そんな日が続くと「自分の身体が弱いのかな」「怠けてるって思われるかも」と不安になるかもしれません。
でも、それは決してさぼっているわけでも、気持ちが弱いわけでもありません。
日常生活の中で身体は、立つ・歩く・座るといった動作のたびに、
血液・神経・骨格が最適なバランスで働くことで
全身の正常な循環で、脳に血液を送り届けています。
起立性調整障害(OD)は
この全身の連動が少しズレた状態で引き起こされる症状のこと。
つまり「気持ちや意志の問題」ではなく、「体の生理学的な不調の問題」です。
だからこそ大切なのは、「どうすればこの正常な循環を取り戻せるか?」ということで
人の身体は「正しい検査」と「正しいアプローチ」をするこで、脳や神経系の機能は改善され「本来のリズム」を取り戻すことができるのです。
起立性調整障害(OD)の特徴
起立性調整障害は
自律神経がうまく働かなくなることで、血流のコントロールが乱れてしまう状態で
特に「立つ・座る」などの体位変化のときに、その影響が強く出ます。
- 朝なかなか起きられない
- 立ち上がると頭がクラクラする
- 動くとすぐ疲れる・息苦しくなる
- 集中できない・ぼーっとする
- 食欲がない、気分が落ち込みやすい
- 頭痛・腹痛・動悸・めまい などが続く
そして、これらの症状は日によって波があり、
「昨日は元気だったのに、今日は全然動けない」ということも珍しくありません。
なぜそのような症状になるのか?
私たちの身体は交感神経と副交感神経という自律神経によって
血圧や心拍を自動で調整しています。
通常、物理的な考えであれば
立ち上がると重力によって下半身に血液が下がるのが通常ですが、
実はこの時に、交感神経が働くことによって血管を収縮させ、脳への血流を保とうとします
しかし起立性調節障害では、この「調整」がうまくいかず、
→ 血管収縮の反応が遅い
→ 心拍だけが上がる
→ 血液が下半身に滞る
などが起こり、脳に十分な血液が届かなくなるのです。
その結果として…
脳が一時的に「酸素不足」になり
・立ちくらみ
・頭痛
・集中力低下
といった症状が引き起こされます。
また、体がだるくなるのは単なる疲れではなく
「血液を脳へ送ることができず、体に血液が鬱滞している」サイン。
朝がつらい理由
夜から朝にかけては、副交感神経が優位な状態でで血圧・心拍が低下していますが
起床時に、交感神経へ切り替える際この反応が遅れた状態で急に立ち上がると
自律神経が切り替わらず、血圧が上がらないまま脳が酸素不足になり倦怠感や頭痛が出やすくなります。
「朝が一番しんどい」というのは起立性調節障害の典型的な特徴で
特に起床時の朝に症状が強く出やすいのです。
起立性調整障害の生理学的メカニズム
1. 立ち上がる瞬間に起こること
私たちが立ち上がると、重力の影響で約500〜800mLの血液が下半身に移動しまが
その瞬間に生理学的な反射的調整が起こります。
①圧受容体反射
頸動脈洞・大動脈弓にあるセンサーが血圧低下を感知し、交感神経を刺激。
→ 血管を収縮させ、心拍数を上げて脳血流を維持しようとします
②筋ポンプ作用
下肢や骨盤周囲の筋肉が収縮し、静脈血を押し上げて心臓へ戻します。
③呼吸ポンプ作用
横隔膜と胸郭の動きによって上肢や頭部に帰る静脈の静脈還流を助けます。
この3つが即座に立ち上がりとともに連動することで、
「立ってもふらつかない」状態を人間は保っています。
2. 反射連動の乱れ
起立性調整障害では、この自動調整がタイミング的にも強さ的にもうまく噛み合わなくなるのが特徴です。
【不調パターン】
| タイプ | 主な特徴 | メカニズム |
|---|---|---|
| 起立直後性低血圧 | 立ち上がってすぐ血圧が下がる | 圧受容体反射の反応遅延 |
| 体位性頻脈症候群 | 血圧は保たれるが心拍だけ上がる | 末梢血管収縮の不足 |
| 神経調節性失神 | 一定時間立位で意識が遠のく | 交感神経の過剰で 副交感神経反射で急低下 |
いずれも、脳への血流(脳灌流圧)が一時的に低下することが共通点です。
3. 脳へ影響
脳は酸素とブドウ糖を非常に多く消費する臓器。
血流がわずかに低下するだけでも、
「ぼーっとする」「集中できない」「立ちくらみ」「頭痛」などが起こります。
特に「前頭葉」や「視床下部」などの自律神経中枢は血流変化に敏感で、
これが繰り返されることで**自律神経系そのものの調整力が乱れやすくなります。
4. 体の使い方の影響
近年では「自律神経だけの問題」ではなく、
姿勢や筋連動、呼吸機構といった構造的バランスの乱れも起立性調節障害を悪化させると考えられるようになり
典型的な例としては
「猫背」や「ストレートネック」による → 胸郭の可動性低下 → 呼吸が浅くなる
骨盤後傾・下肢の筋緊張 → 静脈還流の低下
呼吸筋・横隔膜の働き低下 → 心臓への血液戻りが減る
このように「筋肉・骨格・呼吸・血流・神経」が一体で働けなくなると、
重力に対して姿勢を支える抗重力筋の活動が落ち、
それを補おうとし、自律神経に過剰な負担がかかります
起立性調整障害を「骨格・筋肉」から見る
姿勢バランスの崩れと血流の関係
私たちの体は、立っているだけでも筋肉が常に働き、血液を心臓へ戻しています。
特にふくらはぎや大腿の筋肉は「第二の心臓」と呼ばれるほど、血流維持に重要です。
しかし、
「膝が軽く曲がり、大腿四頭筋に負担が偏る」
「足首の動き(距腿関節)が硬く、ふくらはぎの筋ポンプが働かない」
といった状態では、立位での血液循環が効率的に行えないため
血液が下肢に滞り、脳への血流が減ることで、立ちくらみやめまいが起こりやすくなります。
骨盤・脊柱の「軸」が崩れる
骨盤と脊柱は、自律神経・循環・呼吸のすべてと密接に関係しています。
特に起立性調整障害では、この「体幹の軸」が歪んでいるケースが多くみられます。
たとえば
骨盤の後傾によって腰椎の前弯カーブが失われ、横隔膜の動きが制限されます。
呼吸が浅くなり、胸腔・腹腔内圧のリズムが乱れて静脈還流が滞りを引き起こすパターン
胸椎・肋骨の関節が硬くなることで胸郭が広がりにくくなると呼吸筋(特に横隔膜・肋間筋)の働きが低下し、副交感神経の働きが鈍くなります。
頚椎のアライメント不良は首の筋緊張を持続させ、頸動脈洞への圧力を加えやすくなり血圧反射が乱れやすくなることで、立ち上がり時の血圧制御が不安定になります。
筋肉の「タイミングのズレ」
起立性調整障害の方には、筋肉の“強さ”よりも“タイミング”に問題があることが多いとされ
本来、立ち上がるときは下肢→骨盤→体幹→頸部という順番で連鎖的に筋肉が働くのですが、その順序が乱れることで、身体の血流が乱れます。
たとえば、ハムストリングスや殿筋などの太ももの後面の筋肉はがうまく働かないことで、大腿全面の力が入りすぎたり、腹横筋・多裂筋などの体幹深層筋が遅れて反応することで神経反射を遅延させます。
これらはすべて、重力に対する「身体の支え方の癖」で、結果として循環や神経反射に影響を与えることになります。
「立つこと自体が負荷」になる構造
 健康な状態では、骨格が効率的に重力線上に乗るため、筋肉のエネルギー消費は最小限で済みます。
健康な状態では、骨格が効率的に重力線上に乗るため、筋肉のエネルギー消費は最小限で済みます。
しかし、骨盤が傾いたり、脊柱の正常なS字彎曲が失われることで、重心がズレてしまうことで
静止しているだけでも筋肉が過剰に緊張し、酸素や血流が不足します。
その結果、立位を維持するだけで交感神経が優位になり、疲労感・だるさ・集中力低下が生じやすくなります。
要するに「立っているだけで疲れる」ということになってしまうのです。
脊柱は「神経と循環の要」
脊柱の中には「脊髄」と呼ばれる神経(中枢神経)通り、そこから自律神経が全身に枝分かれしています。
ですから、背骨の関節や周囲の筋膜が硬くなると、その周辺を走る脊髄神経の伝達が鈍くなると
筋肉・血管・リンパの流れも機械的に圧迫されます。
特に影響が大きいのが
頸椎 → 脳への血流を支える椎骨動脈が通過。歪むと脳血流量が低下しやすい。
胸椎 → 心臓・肺・血圧・呼吸中枢と連動し交感神経節が集中するところ
腰椎 → 下半身の血流や姿勢保持に関与し立位時のポンプ作用と関係します
脊柱の歪みがもたらす生理的変化
脳への血流が低下する
頸椎の歪みや緊張により、椎骨動脈の通り道が狭くなると「脳幹・小脳」への血流が減少します。
脳幹には「血圧」「呼吸」「体温」などを司る中枢があり、ここへの血流低下は自律神経バランスに影響します。
呼吸と胸郭の動きが制限される
胸椎や肋骨が硬くなると、呼吸が浅くなります。
呼吸のリズムは自律神経と密接で、浅い呼吸が続くと交感神経優位のままになり、
血管収縮・末梢循環の低下によって倦怠感を感じやすくなります。
骨盤の傾きで姿勢反射が乱れる
骨盤は脊柱の土台です。
骨盤が前後に傾くと、生理的弯曲が崩れることで重心線がズレます。
その結果、頸椎・胸椎・腰椎で代償的な緊張が起こり、姿勢を維持するだけで体が疲れてしまいます。
「背骨のズレ」が神経反射を乱す仕組み
脊柱の両側には、「交感神経節」が縦につらなっているのですが
これは血圧・心拍・内臓機能を調節する「自動制御装置」のようなもの。
これは背骨がねじれたり、筋肉が硬直した時に圧迫ストレスがかかると
その部位の交感神経節が過剰興奮し、反対側は抑制される。
という「左右アンバランスな神経反射」が起こります。
この状態は、圧調整がうまくいかず胸の圧迫感や息苦しさが出る
など、起立性調整障害の典型的な症状が現れやすくなります。
脊柱を整えることで起こる変化
頸椎・胸椎・腰椎の可動性が回復することで
中枢から末梢にかけて多方向の機能変化が起こります。
①背骨の動きに伴う胸郭運動が拡大し、呼吸補助筋の過緊張が解放されることで
→ 呼吸が深まり、迷走神経を介した副交感神経活動が高まる
②頸椎のアライメント改善により、椎骨動脈・脳幹部の血流が円滑化し
→ 立ちくらみや集中力低下といった脳循環不全症状が軽減する
③骨盤:脊柱連鎖の再構築によって、多裂筋や腸腰筋などの姿勢制御筋群の協調性が回復
→ 姿勢維持に必要な筋出力が最小化し、全身のエネルギー効率が上がる
「脊柱の柔軟性は自律神経系の柔軟性そのもの」とも言え
背骨が適切に可動することで、呼吸・循環・神経反射の“緊張と弛緩のバランスを取り戻し
起立性調節障害にみられる生理的アンバランスの改善につながります。
また、これらの構造を整えることは「自律神経を直接操作する」のではなく、
神経や血流の通り道を解放するというアプローチをとります。
つまり、身体の構造を整えることで、機血流・神経伝達・代謝の機能が自然に回復し
自然と起立性調節障害が起こりにく身体が取り戻されていくのです。
起立性調整障害は、身体の仕組みを理解することがスタート
起立性調整障害は、決して「気持ち」や「身体の弱さ」が原因ではありません。
しかし、背骨や骨盤、下肢の筋肉、胸郭や呼吸筋の連動などがズレることで
脳への「血流」や「神経伝達」が滞り、朝のだるさ、立ちくらみ、集中力の低下といった症状が現れるのです。
起立性調節障害は「身体のサイン」であり、体が本来のリズムを取り戻すための注意信号です。
姿勢や筋肉、神経のつながりということを知り、整えていくことが
学校生活や日常の活動を無理なく取り戻す第一歩になります。