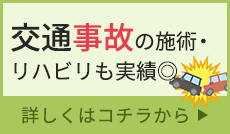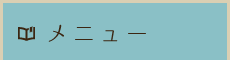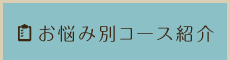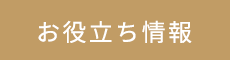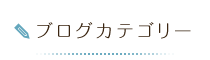岡山の顎関節症治療 | 岡山駅徒歩5分のさくら整骨院
口を開けるとあごが痛い、カクッと音がする、食いしばりや頭痛・首肩こりが続く
顔の歪みが気になるそれは「顎関節症」が原因かもしれません。
生理学的な構造・機能に基づく手技を行うさくら整骨院では、顎関節・咀嚼筋・脊柱・骨盤・姿勢の歪みや神経・血流の滞りを整え、顎関節症を根本から改善します。
顎関節と全身の連動を回復させ、神経や筋肉が本来の働きを取り戻す環境をつくることで、痛みや違和感を和らげるだけでなく、再発しにくい全身のバランス作りをサポートします。
岡山で顎関節症の不快な症状を根本から改善したい方へ
あごのストレスを減らし、これまでの快適で自然な日常を取り戻しましょう。
顎関節症とは?基本の理解
実は、顎関節症はあごや筋肉だけの問題ではありません
首や肩、頸椎・胸椎・腰椎といった脊柱、骨盤といった全身骨格のズレが連鎖的に影響するこによって、顎関節に負担をかけ発症する全身性のトラブル なのです。
軽い違和感やカコカコ音から始まっています
顎のちょっとした違和感は「ちょっと疲れているだけ」と思いがち。ですが、実はそれが 顎関節症の初期サインとして現れることもあります。
- 口を開けたときの「カクッ」という音。
- 食いしばりや軽い痛み。
- あごの引っかかり感。
これらはすべて、体全体の微妙なズレや緊張のサイン。
姿勢や脊柱の歪みが顎の動きに直結する場合もあります。
そして猫背や頭部前方位、骨盤の傾きなど、日常の小さなクセや姿勢の乱れが、首や肩の筋肉に負担をかけ、頸椎・胸椎・腰椎を経由して顎関節にまで影響を与えます。
つまり、あごの不調は あごだけの問題ではなく、全身のバランスが反映された結果です。
「ストレスや緊張も大きく影響する」のが顎関節
精神的ストレスや食いしばり、歯ぎしりが加わると、顎だけでなく首・肩・背中まで筋肉が硬直し、負荷がさらに連鎖することで、あごの違和感や痛みは 複雑な全身の影響のサイン ですから
この解説では「解剖学・生理学・筋肉・関節・脊柱の構造連動の視点 」から
顎関節症の仕組みを詳しく解説し、症状の本質を理解することで、単なる痛みや音ではなく、なぜ身体全体が影響を受けるのか が見えてきます。
気づきにくい初期サインから顕著な症状まで
 顎関節症は症状の出方に個人差があります。
顎関節症は症状の出方に個人差があります。
軽い違和感から始まり、気づかないうちに慢性的な痛みや動かしづらさへ進行することも少なくありません。
顎関節症の代表的な特徴
口を動かすと「あごが痛い」
食事や会話で口を開閉したときに、あごの関節や周囲の筋肉に痛み を感じる
痛みの強さは軽度の違和感から、口を開けるだけでズキッと痛む場合まで様々
特に食いしばりや歯ぎしりをした後に痛みが出やすい
「カクッ」「ゴリゴリ」と音がする
口を開けたり閉じたりすると関節で異音が生じる
音の種類は「カクッ」「パキッ」「ゴリゴリ」など
音がする=必ず痛みがあるわけではないが、関節円板や顎関節の位置にズレがあるサイン となる
口が開けにくい(開口制限)
口を大きく開けられず、指2〜3本分が限界 になることも
円板の前方転位や関節の炎症、筋肉の硬直が原因
食事中や歯磨きで不便を感じる場合は、初期でも注意すべきサイン
あごの違和感や引っかかり感
口を開け閉めする際に ひっかかる、引っかかるような感覚 がある
顎関節の動きが滑らかでないことを示す
「何かが噛み合わない」「あごの動きがスムーズでない」と感じる場合も
顔や首肩の不調を伴うことも
顎関節の問題は、首や肩の筋肉、頭部の神経にも影響するため
関節周囲の神経や血流の影響の連鎖によって 肩こり・首こり・頭痛 が現れることもあり、 耳の痛み、耳鳴り、めまい を伴うことも。
姿勢や脊柱との関係
顎関節は姿勢の影響を強く受けるため猫背や頭部前方位、頸椎の微妙な歪みは顎関節の負担を増やす代表的な原因。
また、長時間のデスクワークやスマホ姿勢で頭が前に出ると、下顎の位置が後方にズレ、関節や咀嚼筋の緊張が強まり、軽い違和感や症状が慢性的な痛みや開口障害に進行することもあります。
代表的な分類
顎関節症は、症状や原因によっていくつかの型に分類されます。
それぞれの型を知ることで、原因や全身への影響も理解しやすくなります。
1. 咀嚼筋障害
あごの筋肉(咀嚼筋)の緊張や疲労が原因で発症し
「口を開け閉めする時の痛み」
「顎周囲やこめかみの張り感」
「首・肩こり、頭痛を伴うことも」
生理学的メカニズム
【筋紡錘とγ運動ニューロン】
咀嚼筋(咬筋・側頭筋など)に長時間負荷がかかると、筋紡錘と呼ばれる筋肉の中にあるセンサー が敏感になり筋肉が反射的に収縮しやすくなります。
γ運動ニューロンと呼ばれる神経は
ストレス・姿勢の乱れ・痛みなどで γ運動ニューロンが過剰に興奮 すると、
筋紡錘の感度が必要以上に高くなり→結果として、軽い動きでも痛みや張り感が生じます。
【血流不足と乳酸蓄積】
筋肉の緊張が持続すると血流が低下、酸素不足で乳酸や代謝産物が蓄積し、痛覚受容器(ノシセプター)が刺激され、顎周囲やこめかみの鈍い痛みやこり感が生じる
2. 関節包・靭帯障害
関節包や靭帯の炎症、損傷が原因
「口を動かすと痛む」
「関節部の腫れや熱感を伴う」場合も
関節の過負荷、外傷、慢性的な関節ストレス
動かすと痛むが、安静時は症状が軽いことが多い
生理学的メカニズム
【関節包・靭帯の炎症反応】
長期の関節負荷や微小外傷で関節包・靭帯に炎症が起き
プロスタグランジンやサイトカインと呼ばれる炎症性物質が放出され、痛みを増幅
【関節液の変化】
炎症により滑液の粘度や分布が変化することで
関節の滑走が不安定になり、動かすと痛みや違和感が増す
【神経の過敏化】
関節周囲の末梢神経が炎症により過敏化し軽い動作でも痛みとして感じやすくなる。
3. 関節円板障害
関節円板の前方転位や変位によって発症
「カクッ」「ゴリゴリ」といった関節音
「開口障害:口が開けにくい」
「口を動かすと痛む場合も」
生理学的メカニズム
【関節円板の位置異常】
円板が前方にズレると、下顎頭と関節窩の滑走が乱れる
これが「カクッ」としたクリック音として認識される
【筋肉の防御反応】
円板のずれにより関節運動が不安定になると、咀嚼筋や側頭筋が反射的に収縮
過緊張により開口障害や痛みが出る
【関節包・靭帯の伸張刺激】
関節が正常な位置を逸脱することで関節包や靭帯が引き伸ばされ、痛覚受容器が活性化。咬合異常、長期の関節負荷、筋肉のアンバランスで起こりやすく
関節の動きが滑らかでなく、軽い違和感が慢性的な症状に進行することも
4. 変形性関節症
顎関節の骨に変形や摩耗が生じるタイプ
開口障害
関節音
動かすと痛む
生理学的メカニズム
【関節軟骨の摩耗・骨棘形成】
関節軟骨が摩耗し骨が直接接触することで、動作時の摩擦が痛みとして伝わる
【関節周囲の炎症反応】
骨変形による負荷増加で関節包・靭帯に炎症が起きやすい動かすと痛む、関節音が鳴る
【神経系の可塑性変化】
慢性的な刺激により、末梢神経や脊髄で痛みの感受性が増大軽い動作でも強い痛みを感じることがある
長期の関節負荷、老化、関節円板異常の進行で
骨の変形により、関節の機能が低下し、慢性的な痛みや動かしにくさが出やすいパターン
顎関節症と脊柱・骨盤の仕組み
顎関節は側頭骨と下顎骨で形成されますが、頭蓋骨全体の頭蓋リズムと呼ばれる動きとも連動しています。頭蓋骨の歪みや緊張は、顎関節の動きや関節円板の位置に直接影響します。
例えば、「側頭骨」や「蝶形骨」の僅かな位置変化でも、咀嚼筋の緊張や関節円板のずれにつながります。
脊柱・骨盤との連鎖
頸椎の歪みや胸椎の後弯、腰椎や骨盤の傾きは、顎関節の位置や下顎の動きに影響します。
顎関節と脊柱の関節可動性は 「連鎖的な運動連動」 と考えられています。
顎関節と脊柱の連鎖的運動
頸椎と顎関節の関係
上位頸椎(C1・C2)の可動性低下は、頭部や顎の動きを制限します。
頸椎の歪みや可動性低下は、三叉神経や迷走神経の緊張を引き起こすことで
顎関節痛や違和感
咀嚼筋の防御的過緊張
頭痛、耳鳴り、めまいなどの関連症状を引き起こします。
中下位頸椎(C3〜C7)の変位は、肩甲帯・僧帽筋・胸鎖乳突筋の緊張を増幅し、結果として咀嚼筋や下顎の動きに負荷を与えます。
胸椎(背骨)の影響
胸椎後弯(猫背)は、肩甲骨や胸郭の位置を変化させます。
胸郭の硬さ・動きの制限は、肩甲骨周囲筋の過緊張を引き起こし、その連鎖で咀嚼筋も過緊張状態に。呼吸パターンにも影響し、浅い呼吸になると副交感神経の働きが低下し、全身の緊張が持続。その結果、顎関節の動きが制限され、開口障害やクリック音、痛みが現れます。
腰椎・骨盤との連鎖
骨盤の前傾・後傾や左右差は、脊柱全体のアライメントに影響。
脊柱の傾きは頸椎の位置や頭の重心を変化させ、下顎の位置にも連動。
骨盤の歪みによる重心の偏りは、肩・首・顎への筋緊張を生み、顎関節症状を増幅する要因となります。
血流・神経の連鎖
血流・リンパの循環が顎関節に与える影響
咀嚼筋(咬筋・側頭筋・翼突筋)が慢性的に緊張すると、筋内部の毛細血管が圧迫され、局所の血流が低下します。血流が滞ることで酸素や栄養の供給が制限され、乳酸などの代謝産物が蓄積しやすくなります。結果として、筋肉はさらに硬直し、顎関節の動きが制限される悪循環が生まれます。
また、顎関節や顔周囲のリンパ管は頭蓋底や頸部を経由して全身とつながっています。筋肉や関節の緊張が続くことでリンパの流れが滞り、老廃物や炎症性物質が排出されにくくなります。その結果、顎や顔、耳周囲にむくみや違和感が生じやすくなるのです。
顎関節症は全身のサイン
ン顎関節症は「あごや筋肉だけの問題ではありません」
首や肩、脊柱(頸椎・胸椎・腰椎)、骨盤、さらには全身の血流・神経の状態までが影響し、連鎖的に顎関節に負担をかけることで症状が現れます。
つまり、顎関節症は全身のバランスの乱れがあらわになったサインです。
このサインを初期の状態で知り、早期に顎関節症を改善することで
長期的な改善が必要となるレベルまで悪化することなく、顎関節症の早期改善を行うことができるのです。