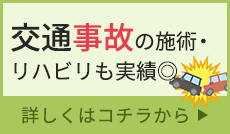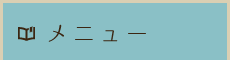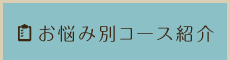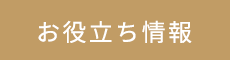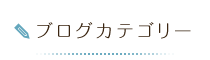整体から筋膜リリース・カイロプラクティックまで手技療法の分類と違いが一目でわかる!
ひとえに、手技療法(マニュアルセラピー)と言っても
その生まれた歴史か文化や歴史的背景、哲学などが混ざり合い
世界各地で独自に考案され
現代のの整骨院や病院のリハビリの現場で使われています。
その起源とも言える手技「マッサージ」
中国の推拿「すいな」
インドのアーユルヴェーダ
日本でお馴染みの「あん摩」など
いわゆる「マッサージ」と呼ばれる手法は
古代から行われているとされ
軽くさする「軽擦」
強くさする「強擦」
リズム良く叩く「叩打法」 → 日本伝統の肩たたきがまさにコレ
もむ「揉捏法」
これら全ての手法が「マッサージ」に分類されます。
次に19世紀後半から近代にかけて生まれてのが「徒手療法」
オステオパシー
1874年に「アンドリュー・テイラー・スティル」というアメリカの医師が
医療の開拓時代の当時、薬や外科手術の安全性が低くく
医師として活動しながらも
自分の子どもたちを当時の感染症で亡くした経験から
薬に頼らない手法を模索し
「オステオパシー」
という療法を提唱しました。
スティルは1892年に米国初のオステオパシー専門学校を設立し
現在、アメリカではDO「Doctor of Osteopathic Medicine」
という正式な医師資格になっており
薬物投与・手術も含めた医療行為も可能な
「医師」同等の水準で医療を行える権威性を有しています。
語源は
Osteo(骨)+ pathy(療法・方法)というところからで
そのまま読めば「骨療法」に見えますが
実際は
全身の構造(骨格・筋・結合組織)と
機能(神経・血流・内臓)のバランスを整える
という意味をさすそうです。
カイロプラクティック
その時期と同じくらいのタイミングの1895年に誕生したのが
ダニエル・デイヴィッド・パーマーによる
カイロプラクティック
こちらはアメリカ・アイオワ州で活動していた施術家で
元々は磁気療法など代替療法を行っていたところ
聴覚障害をもつ清掃員ハーヴェイ・リラードの背骨の“ズレ”を矯正したところ
聴力が回復したという出来事をきっかけに
カイロプラクティック(Chiropractic)を提唱。
カイロプラクティックの語源はギリシャ語で
↓
「cheir(手)」+「praktikos(行う)」=「手による技術」Chiropractic
という造語から生まれ
誕生初期は「ストレート・カイロプラクティック」として
脊椎のアジャストメント(矯正)が行われていましたが
その後、様々な考え方や哲学から多様なテクニックが考案され
代表的な手技として
ディバーシファイド(最も一般的な手技矯正)
ガンステッド(精密X線評価による矯正)
トムソン(ドロップテーブル使用)
アクティベーター(器具で軽い刺激を加える)
SOT(仙骨後頭骨テクニック)
ローガンベーシックなどが誕生
関節モビリゼーション、MET、PNF
こういった流れとは別に20世紀半ば以降の欧米では
医学教育を受けた理学療法士が実際の臨床経験と神経生理学の研究に基ずいて
新しい徒手療法を体系化し
オーストラリアのジェフ・メイトランドらが体系化した
関節モビリゼーション
米国の理学療法士がオステオパシーの考え方を取り入れつつ発展させた
MET:マッスルエネルギーテクニック
アメリカの神経生理学者カバットらが開発じた
PNF(固有受容性神経筋促通法)
などが生み出せれました。
スポーツの分野への応用
近年では、スポーツの分野に手技が取りいられるようになり
スポーツマッサージ
リンパドレナージ
トリガーポイント療法
など
軟部組織を対象にした近代的マッサージが普及しています。
目的やアプローチ別の分類
こう言った歴史から、目的やアプローチする組織によって
様々な手技が考案されており、それらを大きく分類すると
筋や筋膜・皮下組織や・リンパに対する手技の
軟部組織系
カイロ・関節モビリゼーションなどの脊柱や関節に対する
背骨・関節系
PNFやマッスルエナジーテクニックと言った
神経・運動系
オステオパシーやSOTなどの
頭蓋・全身調整系に分類されます
マッサージ・軟部組織手技
|
伝統的手技 |
日本のあん摩に由来する基本手技で摩擦・圧迫・振動を組み合わせて血流改善を図る |
|
スポーツマッサージ |
運動前後の疲労回復を目的にした筋・関節へのマッサージ |
|
筋膜リリース |
筋膜の癒着・緊張を緩め血流を改善 |
|
トリガーポイント療法 |
痛みの引き金点(トリガーポイント)に圧刺激を加え |
|
リンパドレナージ |
リンパの流れと静脈還流を促し |
|
指圧・タイ式・リフレクソロジー |
経絡・ストレッチ・足裏反射区など東 |
カイロプラクティック(脊椎矯正中心)
|
ストレート |
哲学重視でサブラクセーション(椎骨のずれ)の |
|
ディバーシファイド |
最も一般的な手技矯正。 |
|
ガンステッド |
レントゲン分析を用い、骨盤や脊椎の配列を精密に評価し矯正する方法 |
|
トムソン |
ドロップテーブルを使用し、 |
|
アクティベーター |
専用器具で軽い刺激を与え |
|
アプライド・キネシオロジー |
筋肉テストで機能異常を評価し |
|
SOT |
仙骨と後頭骨のバランスを重視し |
|
ローガンベーシック |
仙骨への軽い圧で全身バランスを整え、 |
関節モビリゼーション/徒手療法
|
メイトランド・マニュアルセラピー |
関節の可動性や痛みの評価・改善を目的とした |
|
マクケンジー法 |
自己運動と評価を組み合わせ、 |
|
マリガン |
患者自身の運動とセラピストによる関節矯正を |
|
AKA-博田法(関節運動学的アプローチ) |
関節運動学の原理に基づき、関節の運動性と神経機能を評価・改善する手技 |
|
マッスルエネルギーテクニック(MET) |
患者の自発的筋収縮を利用し、関節可動域や筋の緊張緩和を促す徒手療法 |
神経・運動促通系
|
PNF(固有受容性神経筋促通法) |
神経生理学に基づき、関節可動域や筋力・協調運動を改善するために、特定の姿勢や抵抗運動を組み合わせて行う手技 |
|
AK(アプライドキネシオロジー ) |
筋肉テストで身体の機能異常を評価し、矯正や全身調整を行う手法で、神経筋連鎖や関節機能との関連を重視 |
さくら整骨院で採用しているオステオパシー
この中で、当院で使用しているのは
「オステオパシー」という手法で
スコットランド出身の医師で、A.T.スティルの弟子の一人である
リトルジョン(1865–1947)が提唱した理念に基づいた手法です。
この手法は、科学的根拠に基づいて
全身の構造と機能のバランスを整えるアプローチを提供しており
患者自身の自然治癒力を最大限に引き出すことを目的としています。
このリトルジョンという医師は
米国でオステオパシーを学んだ後
1917年にイギリスで「現在の University College of Osteopathy」を創設し
オステオパシーを欧州に広めた中心人物で
「アンドリュー・テイラー・スティル」のオステオパシーの理念を解剖学・生理学・運動学など科学的基盤と結びつけて整理し体系化し
「脊柱だけでなく全身の循環・神経・内臓との関連を重視する」
という視点を強調し現代のオステオパシーの枠組み作りに大きな影響を与えた人物です。
このオステオパシーという手技は
創始者で外科医でもあったアンドリュー・テイラー・スティルが当時の薬物中心の医学に疑問を持ち、「自然治癒力を最大限に引き出す」手技療法を模索し
解剖学・生理学に基づき、構造と機能のバランスを整える概念から生まれ
オステオパシーは、骨格だけでなく全身の構造と機能の調和を重視し、自然治癒力を最大限に活かすという思想から始まった手技療法です。
スティルが提唱した4原則
- 身体はひとつの統合された単位
身体・心・精神は分けられないという考え方。 - 身体には自己治癒・自己調整の能力がある
薬に頼るのではなく、構造を整えることで自然治癒力が働く。 - 構造と機能は相互に関係する
骨格や筋膜などの構造の乱れは、神経・血管・リンパなど機能系の障害につながる。 - 合理的治療はこれら原理に基づく
という人の身体の原理原則の視点が
後のカイロプラクティックや現代徒手療法に大きな影響を与えることとなります。
手技の特徴として
骨格矯正だけでなく筋膜・内臓・頭蓋も手技の範囲
オステオパシーでは、筋骨格系だけでなく、
内臓の可動性や頭蓋骨の微細な動きを調整する手技もあり
評価(検査)を非常に重視
可動域・組織の質感・循環状態など、手で「診る」ことを重視する。
薬物・外科の補完
米国では現在も医師資格(DO)ドクターオステオパシーとして制度化されており
薬や手術も行える「オステオパシー医」として活躍されています。
オステオパシーの派生
スティルの弟子や後継者から
さらにオステオパシーは派生し
頭蓋オステオパシー(W.G.サザーランド)
フェシリテイテッドポジショナルリリース
ストレイン・カウンターストレイン
など多くの手技が生まれ
この「構造と機能をみる」という視点は、理学療法士のマニュアルセラピーや
カイロプラクティックにも影響を与えている考え方となっています。
どうやってオステオパシー学んでいるの?
実は、このオステオパシーという技術も
前述したように「さまざまな流派が派生」し、そのレベルも様々。
日本でも、オステオパシー協会という団体もありますが
実は、近年。
このオステオパシーという手法の権威性がさらに高まり
以前は、日本で国家資格を取得していれば
外国のオステオパシーの講座を受講することも可能だったのですが
現在は、医師のレベルでなければ
海外で開催されているセミナーすら参加できない状況になってきています。
ですから、日本人が海外でオステオパシーを学ぶ環境というのが、今後かなり厳しくなってくるのですが幸いなことに、知人を通じて、海外のオステオパシーに精通する方から学ぶ機会を頂けており
なかなか、与えてもらえない貴重な人脈で世界的にもレベルの高いオステオパシーを現在も学び続けさせていただけていることで、世界の高い水準の技術の一部を常に患者さんにご提供させていただけております。