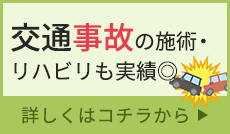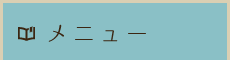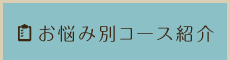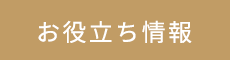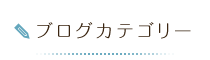身体が不調な理由を整体師が徹底解説
肩こりがひどくて……
腰が痛くて仕事に集中できない……
そんな時、多くの人がまず思い浮かべるのが
「マッサージ」
実際、マッサージを受けた直後は、身体が軽くなって痛みやコリが和らぐように感じます。
しかし、一方で
「マッサージは全く意味がない!」
という表現がされることもあります。
コチラの記事で紹介しているように
⬇︎⬇︎⬇︎
マッサージは歴とした古代からの伝統的な
手技(マニュピレーション)であり
生理学的視点からもても
「意味がない」ということはありません!
ですが、それがあなたの望んでいる
「結果」
と違う。
そういう可能性について生理学の視点から、マッサージだけでは不十分なケースと身体が不調になる原因を体のメカニズムも交え詳しく解説していきます。
マッサージの効果期間
よく、マッサージ問題で取り上げれやすいのが
効果の持続期間
もちろん、他の方法と比べて
持続効果や改善力が低くなってしまうのは仕方のないことなのですが
その仕方がない理由というのは
マッサージという手法は
「筋肉」や「リンパ」と言われる軟部組織に対して
アプローチする方法なので
どうしても効果の期間が長続きせず
数日後に同じ症状に悩まされてしまうという
これが、俗によく言われる
「マッサージに通っても、改善しない」と言われる理由。 マッサージで得られる効果って?
マッサージで得られる効果って?
では、マッサージにどのような効果があるのかというと…..
1、筋肉の一時的な緩和
マッサージを受けると 硬くなった筋肉がほぐれることで血流が改善され
老廃物が蓄積されたコリや交感神経による身体の張りが緩和されることで
施術中や、直後に身体が楽になりリラックスします。
純粋に、身体の緊張が取れて筋肉や関節を巡る血液量が増加することで
例え一時的であれ、身体はいい状態に改善します。
ここでは、一時的と書きましたが
実際、朝から晩まで
「マッサージ→入浴→マッサージ→入浴→マッサージ→入浴→マッサージ→入浴→マッサージ」
を繰り返せば、「身体の循環と硬さ」はかなり改善されると思います。
ですが、このマッサージ ↔︎ 入浴法も
運動と同じ理論で
なんでもやりまくればいい!というものではないので
どれだけマッサージを受けるとしても
「1日に2回」も繰り返せば
身体にとっては相当負担になると思ってもらって良いかと思います。
2、リンパ液の流れの改善
そして、血液の次の話は「リンパ」
先ほどは「筋肉の話で血流」の話をしましたが
当然マッサージによって
「局所的にも、全身的にリンパ」の流れも促進されます。
実は、リンパ液は「体のもう一つの血液」とも呼ばれる透明な液体で
「免疫」とも非常に深い関わりをもつのですが
血液が「酸素や栄養を運ぶ一般道路」とするなら
リンパは「老廃物や異物を回収し続け身体守る高速道路」で
リンパ液は身体の中の細菌やウイルスなどの「敵」を捕まえ
リンパ節へ届けます。
リンパ節では白血球(リンパ球)が集まって待ち構えており
そこで「敵を分析&攻撃」して撃退。という流れ。
これは、風邪などで喉が腫れるメカニズムで
1、風邪ウイルス → リンパで回収
2、ウイルス分析期間中 → 喉腫れない(無症状)
3、分析終了 → 段々腫れる → 総攻撃で一気に腫れる
ですから
風邪の「腫れと熱」は撃退真っ最中。
の後半戦。
それともう1つリンパ液の重要な役割が
「置き去りになった老廃物やを水分を回収すること」
これがよく美容分野などで説明される
「むくみ」の仕組み。
実は、血管というのは「完全に密閉された筒」になっているのではなく
いくらか、血管の外と内を液体や物質が通過できるようになっています。
そういう構造になっていることから
血液を流れる「水分」が血管の外に漏れ出て身体の外に滞留する。
その正体が「むくみ」です。
そしてその身体の外に滞留する水分をすくい上げて
再び血液に戻すのがリンパです.
リンパの流れに沿って適切にマッサージをしてあげることで
血管の外に漏れ出た水分をリンパが回収することで
むくみがスッキリし、重だるかった身体が軽くなる
という変化が出るのです。
これがリンパマッサージで体がスッキリする生理学の仕組み。
3、リラクゼーション効果と自律神経への影響
あとは純粋にマッサージを受けることで副交感神経のスイッチが入ることによる
心身がリラックス状態に。
これによりストレスが軽減され結果として睡眠の質が向上することも。
精神的なリラックスを得られる点もマッサージの大きなメリット!
身体を触られるのが苦手な人は逆効果になってしまう人もいますが
上手な人にマッサージしてもらえると
気分がリラックスする人も多いのではないでしょうか?
ですから、このように
マッサージには「マッサージで得られるメリットと効果」があるのです。
…….が
最初にお伝えした部分のあなたの望んでいる
「結果」という場合。
それが「一時的な対処」と言われてしまう場合が多く
これが
「身体の根本的原因」を改善できているのか?
となってしまうと
それは、求めている「結果」とは少し違うのかもしれません。
マッサージだけで不十分な理由
では、なぜマッサージだけでは身体の不調が改善しないのか?
根本原因にアプローチしてないから
通常、ほとんどの人が
「腰が痛い場合」は腰の筋肉が凝っている
「肩が痛い場合」は肩の筋肉が張っている
と考える人が多いのですが
実際、肩こりや腰痛の多くは 「筋肉だけの問題でなく」
「姿勢の歪み」「関節の可動域制限」「日常動作のクセ」などの
複合的要因が絡み合って症状を引き起こしています。
ですから
マッサージは筋肉の緊張は解きほぐしきますが
姿勢や関節の位置関係の問題はそのまま残ってしまい
また同じ筋肉に負担がかかってしまうのです。
身体が不調になる本当の理由
1. 姿勢の崩れ
現代人の多くはパソコンやスマホを長時間使うことで
いつの間にか自然に画面を覗き込んでおり
いわゆる、前かがみや猫背の姿勢と言われる形の姿勢を続けています。
こういった姿勢不慮が長時間長期間続くことで
「背骨」や「骨盤」、「下肢の位置」はズレ
座った時や立ち姿勢、歩き方などで特定の筋肉に負担が集中しやすくなります。
人間の頭の重さは 約5キロもあると言われているので
頭とアゴが前に出るような姿勢では
頭の重さが常に「首」や「首の付け根」「肩」の筋肉にかかることで
段々と周囲の血流量は低下し組織が固くなり
「肩こり」のような症状が作られるのです。
また、これが長期間行われれば
首や肩の骨の位置関係は
正しい位置からズレやすくなり首や肩にかかる負担は倍増!
結果的に、ただの肩こりが
「首の寝違え・頭痛・めまい」
といった症状に進化していくのです。
2. 関節の可動域制限
生き物というのは、年を重ねるごとに
体の中に貯蓄しておける「体水分量」というのが
減少することで、どうしても若い時と比べて乾燥しがちになってしまいます。
| 年齢層 | 体水分量(%) | 特徴 |
|---|---|---|
| 新生児(0歳) | 約75~80% | 体の大部分が水分で構成され脱水に弱い。 |
| 乳児(1歳前後) | 約70% | 成長とともに細胞の中の割合が増える。 |
| 小児(学童期) | 約65% | 体格や筋肉量に応じて成人に近づく。 |
| 成人男性 | 約60% | 筋肉量が多いため水分比率も高い。 |
| 成人女性 | 約50~55% | 脂肪組織が多く筋肉量が少ないため男性より低い。 |
| 高齢者 (65歳以上) |
男性 |
加齢により筋肉量が減少し、 脂肪が増えるために水分比率が減少。 |
この表で見てわかるように、極端な話
新生児と高齢者では「2倍ほど水分保持力」は違います!
ですから
当然、水分量が低下するとともに
筋肉や靭帯といった軟部組織に巡る水分量も低下し、乾燥しやすくなってくるので
それに伴って全身の関節や脊柱も硬くなりやすくなってきます。
また、肩関節・脊柱・股関節、肩甲骨、などの
関節と呼ばれる部分が硬くなってくると関節が動く可動域が低下します。
この関節が、本来の役割を果たせなくなると
筋肉が関節の代わりに余計に働かなければならないので
さらに疲労が蓄積しやすくなるという仕組み。
例えば肩甲骨の動きが悪ければ
腕を上げる時に
首や肩の筋肉群がいつも以上に大きな力を使って腕を上げなければいけない。
という身体のバイオメカニズムで
典型例としては
「膝関節」あるいは「股関節」が硬い人は
その動きを腰の筋肉でカバーしようとするため
非常に腰痛が起きやすくなります。
3. 筋肉バランスの崩れ
SNSなどで耳にするインナーマッスル。
これは筋肉の中でも
表面に位置するの大きな筋肉「例えば胸部であれば 大胸筋 」と
深層のインナーマッスル 前鋸筋 がバランスよく動きが連動して動くことで
無駄なく効率的に体が動くのですが
普段の日常生活では
ついつい表面の大胸筋などの大きい筋肉だけをつかて生活を送ることが多いため
インナーマッスルとアウターマスウルのバランスが崩れ
身体を支えるインナーマッスルの力が低下することで
特定の部位に負担がかかりやすくなってきます。
これは、よく肩で症状が見られることが多く
アウターマッスルの三角筋と
インナーマッスルの棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋
のバランスが崩れて
ボールを投げる時に肩の痛みが強くでたり、肩が上がらなくなったりする。とういう症状で
無自覚にバランスが崩れてしまっていることがほとんどなので
強い症状が出てからその不調に気づく方がほとんどです。
4. 自律神経の乱れ

自律神経については、近年、益々症状を訴える人が増えてきていますが
「睡眠不足」「ストレス」「過労」「などにより
常に交感神経が優位な状態が続くと
筋肉が常に緊張状態になり、それと同時に血流の低下を招くことで代謝が低下し
疲労物質が体内に蓄積しやすくなるという生理学的な反応の流れ。
結果として、自律神経の乱れは
肩こりのみに収まらず
「頭痛」「冷え症」「乾燥肌」「めまい」「PMS」などさまざまな不調を引き起こします。
現代社会では ストレスや不規則な生活によって
自律神経が乱れやすい環境になることが多いため
このメカニズムによる慢性的な身体の不調を訴える方が非常に多いのです。
筋肉だけにアプローチしても根本解決にならない
こういった
「姿勢の崩れ」
「関節可動域の制限」
「筋肉バランスの乱れ」
「自律神経の乱れ」
といった原因をもとに、体というのは硬くなり、不調を訴え、痛みへと進化しています。
ですから
筋肉をもにほぐして、血流を改善する「マッサージ」は
手技を受けた時には筋肉がほぐれて楽になります。
硬くなった筋肉が柔らかくなる感覚や
血流が改善し心地よさを実感する人も多いと思いますが
これはあくまで 一時的な緩和で
慢性的な肩こりや腰痛や首肩の痛みの多くは
結局、筋肉だけの問題で起こっているわけではなく
様々な要因が重なり、関節や骨まで影響することによって
継続的に起こっているのです。
ですから、マッサージをした後に
症状が戻ってきてしまうのは仕方のないことで
慢性的な痛みを改善するためには
関節、骨、神経、靭帯など もっと広い視点から身体を整えることが必要なのです。
マッサージの適応と根本治療
痛みや症状は「壊れた場所からの警報」で
体・心・環境の総合信号です。
ですから
日々の「身体の疲れを洗い流し」リラックスした時間を過ごす。
そういう目的の時には、マッサージは最高に良いでしょう
しかし、あなたの望んでいる「結果」が
慢性的な血行不慮で
筋肉だけにとどまらず
関節や脊柱、神経や内臓、姿勢やバランスなど
軟部組織以外の影響に及んでいるのであれば
その症状や痛みは、違ったアプローチで改善しなければならないかもしれません。
現代の慢性的な不調は、単に筋肉の硬さだけでなく、
「姿勢・関節の動き・神経の働き・自律神経のバランス」といった
身体全体のつながりの乱れによって引き起こされています。
ですから、その背景にある構造的・生理学的な原因に目を向け、
全身のバランスを整えることこそが、本当の意味での「根本改善」です。
身体は本来、自ら回復しようとする力を持っています。
その力が正しく働ける環境を整えてあげることで、
痛みや不調は自然と軽減し、日常の動きや呼吸までもが変わっていきます。
「ほぐす」 から 「整え統合する」
それが、慢性的な痛みを繰り返さないための、最も確かな道筋です。